こんにちは、奨学金男です。
職場や日常で、「あの人、気が利くなあ」と感じる瞬間ってありませんか?
空気を読んで動ける人、誰かが困っているときにサッとフォローできる人。
そういう人を見ると、「この人、仕事できるんだろうな」と、自然に感じてしまいます。
実際、私の周りでも“気が利く人”はだいたい仕事もできる印象があります。
段取りがうまくて、ミスが少なく、周囲との連携もスムーズ。
結果的に、評価されるのはそういう人たちです。
一方で私はというと……。
自分のことで手一杯で、他人に気を配る余裕がなく、
「あれ? これ、誰かやってくれてると思ってました」なんていう凡ミスも日常茶飯事。
正直、「気が利く人間」には程遠いと感じています。
今日はそんな私が、「どうすれば気の利く人間に近づけるのか?」
を、自分なりにざっくり考えてみた話を書いてみたいと思います。
「気が利く=才能」ではない(と信じたい)
まず前提として、気が利くというのは「生まれ持った才能」ではないと信じたいです。
もちろん、気配りが得意な人や、空気を読むのがうまい人はいます。
でも、それって訓練や経験である程度身につく力でもあるはずです。
私のように、不器用で気が回らない人間でも、
「こういう場面では、こう動くと助かる」
「こう言ってくれたらうれしい」
そういう“積み重ね”を学んでいけば、少しずつ近づけるんじゃないかと思っています。
「気を利かせる」って、何をすること?
そもそも、“気を利かせる”って、どういうことなのでしょうか。
私が感じるのは、こんな場面です。
- 会議の準備で誰かがバタバタしているとき、黙って資料を配ってくれる
- 混雑している社内で、さっと場所を譲る
- みんなが忙しいとき、差し入れをそっと置いてくれる
- 上司が欲しがりそうなデータを、言われる前に整理しておく
大げさなことではなく、「ちょっとした一歩先の行動」。
たったそれだけで、空気が変わる。助かる人がいる。
だから“気が利く”人は、自然と感謝されて、信頼されるんですよね。
私にできる「ざっくり」な気配り訓練
では、そんな“気が利く人”になるには、どうしたらいいのか。
もちろん、完璧を目指したらしんどくなってしまいます。
私は要領も悪く、余裕もあまりないので、大それたことはできません。
でも、「ざっくりと気が利く人」になるために、こんなことを意識してみようと思っています。
1. 自分以外の人を1日に1回、観察してみる
意外と、自分以外の人の“困りごと”って目に入っていないことが多いです。
エレベーターで荷物を持ってる人がいたら、開ボタンを押すとか、
同僚が資料探してたら、「これじゃない?」と声をかけるとか。
「1日1回だけ、誰かを見る」それくらいなら、不器用な私にもできそうです。
2. 「困ってるかも?」と思ったら声をかける練習
私のようなタイプは、「声をかけて邪魔だったらどうしよう」と考えて動けないことが多いです。
でも、たいていの場合「声をかけてくれてうれしい」と思ってもらえる気がします。
「やりすぎたら迷惑かも」と萎縮する前に、
「軽く声をかける」ぐらいのフットワークで試していきたいです。
3. 自分の“失敗パターン”を見直しておく
過去の自分を思い返すと、だいたい同じようなところで気が利かず、
「またやっちゃった……」となることが多いです。
私は、「言われたことしかやらない」「見て見ぬふりをしてしまう」
この2つのパターンが多い。
だから、「こういう時こそ、声をかける」と決めておくと、少しだけ行動しやすくなります。
気が利くことは「評価」につながる
実際問題として、職場では“気が利く人”の方が評価されやすいです。
なぜなら、そういう人は「安心して仕事を任せられる」からです。
私も、できればそう思われたいです。
借金がある身としては、少しでも仕事で信頼されて、
収入を安定させることが、生きる上での優先事項でもあります。
ただ「評価されたいから気を利かせよう」と思ってやると、
だんだんしんどくなるので、「自分のクセづけ」の一環としてやる。
それぐらいの心構えで、続けていきたいと思っています。
気が利く人間に、私はなれるだろうか
正直、まだ自信はありません。
でも、「少しずつ近づく」ことなら、できる気がしています。
気が利く人は、観察力と想像力がある人だと思います。
そしてそれは、日々の中で磨いていけるスキルでもある。
私のように不器用で、気づいたら自分のことで精一杯になってしまう人間でも、
小さな“気づき”と“小さな行動”を積み重ねていけば、
「お、気が利くじゃん」と思ってもらえる瞬間が、いつか来るかもしれません。
自分を変えたいと思ったとき、何から始めるか。
その答えのひとつとして、「気を利かせてみる」——それは案外、いいスタートなのかもしれません。

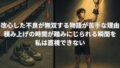

コメント