こんにちは、奨学金男です。
今日、ニュースで目にした記事に胸が詰まりました。
政府が発表した「2025年版自殺対策白書」によると、2024年の15~29歳の若者の自殺者は3125人。
5年連続で3000人を超えているそうです。
数字で言えば、ただの「統計」かもしれません。
でも、その一つ一つの背後には、誰かの人生、誰かの苦しみ、そして「もう無理だ」と思った夜があったはずです。
私も、そんな夜を何度も経験してきました。
「死にたい」と思った夜のこと
私は高校2年のときに父を亡くし、母子家庭で育ちました。
その後、3浪して私立の6年制大学に進学し、国家資格を取りました。
けれど、その代償として背負った奨学金の総額は2100万円を超えています。
返済が始まってからというもの、生活は常に綱渡りです。
毎月の返済額、家賃、光熱費、食費。
どれをとっても「余裕」という言葉とは無縁で、将来の見通しが立たない日々が続いています。
そんな生活の中で、何度か「もう消えてしまいたい」と思ったことがあります。
夜中に布団の中で、息が詰まりそうなほどの孤独を感じるとき。
自分の存在が誰にも必要とされていない気がして、どうしようもなく虚しくなる瞬間がある。
それでも、私は「死ぬ」という行動には移せませんでした。
それは「勇気がないから」かもしれません。
でも、同時に「もう一度だけ生きてみよう」という、わずかな希望にしがみついた結果でもあります。
自殺という“最終手段”が選ばれる社会
白書の中で特に気になったのは、「若い女性のオーバードーズ(市販薬などの過剰摂取)」の増加です。
20~30代前半では、自殺未遂歴がある人の4割以上がODで搬送されているとのこと。
40歳未満の未遂者の6割がODを選んだというデータもありました。
薬局で手に入る薬を“死の手段”にする――。
それほどまでに、彼女たちは追い詰められているということです。
SNSを見れば、「死にたい」「もう疲れた」とつぶやく若者が数えきれないほどいます。
中には「助けて」と言葉にできず、静かに姿を消してしまう人もいます。
「なんでそんなことを」と他人事のように言う人もいますが、
実際は、誰だってそうなる可能性があると思います。
特に、経済的にも精神的にも支えが少ない若者ほど、
“死にたい”という言葉に現実味を感じてしまうのです。
貧困と孤立が、心を蝕む
貧困は、ただお金がないというだけの問題ではありません。
お金がないと、「希望」まで削られていく。
将来を想像できず、「どうせ何をしても無駄」と思い込んでしまう。
そうやって、心が少しずつ壊れていくのです。
お金がないと友人と遊ぶ余裕もなく、どんどん疎遠になってしまいます。
そんな生活をしていると、人との会話が減り、外に出る気力もなくなっていきます。
やがて「誰も自分を見ていない」「このまま消えても誰も困らない」と思うようになる。
それが孤立の始まりです。
そして、孤立は確実に心をむしばんでいきます。
人は、誰かとつながっていないと、簡単に壊れてしまう。
だからこそ、貧困と孤立は自殺リスクを大きく高めるのだと思います。
「死にたい」と思ってもいい。でも、そこで止まってほしい
私は「死にたい」と思うことを否定するつもりはありません。
むしろ、その気持ちを無理に押し込める方が危険だと思っています。
生きづらい社会で、真面目に働いても報われない現実がある中で、
「もう無理だ」と感じるのは自然な反応です。
ただ、そこで“止まってほしい”。
一晩でいいから、やり過ごしてほしい。
「明日になったら少しマシかもしれない」と、
ほんの少しだけ自分を信じてみてほしいのです。
人間の感情は波のようなもので、
どんな絶望も永遠には続きません。
そして、その波を乗り越えた先にしか見えない景色が、必ずある。
私はそのことを、身をもって知りました。
「理解できない」けれど、理解しようとしたい
正直に言えば、私は「自殺を実行した人の気持ち」を完全には理解できません。
理解できるなんて軽々しく言うのは、きっと不誠実です。
でも、「理解しようとすること」はできると思っています。
死を選んだ人を責めたくない。
ただ、そうなる前に、誰かに「もう少しだけ生きてみよう」と言ってもらえたら、
結果は違っていたかもしれない。
そう思うと、やりきれない気持ちになります。
「死にたい」と思う人の隣に、誰かが静かに座っているだけで、
人は救われることがあります。
言葉よりも、「存在」が希望になる。
そんな社会であってほしいと、心から思います。
本当に必要なのは、“理解されること”
自殺対策白書には、
「救急搬送後に再び自殺を試みないよう、包括的な支援が必要」とあります。
その通りだと思います。
でも、支援の前に大切なのは、「理解されること」だと私は感じます。
「そんなことで悩むな」「もっと頑張れ」。
そんな言葉を浴びせられると、人はますます孤独になります。
必要なのは励ましではなく、共感です。
「つらいよな」「わかるよ」――その一言で、
人はもう一度、生きようと思えることがある。
生きることに“意味”がなくてもいい
誰かが言いました。
「生きる意味なんてなくていい。生きてるうちに見つかることもあるし、見つからないままでもいい」と。
私はその言葉に何度も救われてきました。
奨学金返済に追われ、将来の希望もなく、
それでも今日も働いて生きている。
それは立派なことです。
意味がなくても、生きているだけで十分なんです。
それでも、前を向きたい
自殺が減ることは私の願いです。
けれど、それを口にすることすら「余計なおせっかい」なのかもしれません。
誰かの苦しみを完全に理解することはできないし、
「生きろ」と言うことが暴力になる場合もある。
それでも私は、
「みんなが前を向いて生きられる社会」になってほしいと思います。
そして、自分自身もその社会の中で、
小さくても前を向いて生きていきたい。
おわりに:生きることは、戦いではなく、選択
生きることは戦いじゃない。
勝つ必要なんてないし、立派である必要もない。
ただ、「今日を生きる」という選択をすること。
それだけで、十分すごいことです。
もし今、あなたが「もう疲れた」と思っているなら、
とりあえず今日は何もせず、眠ってください。
明日になれば、少しだけ世界の色が変わるかもしれません。
私もそうやって、何度も朝を迎えてきました。
だから、あなたも――
もう少しだけ、生きてみませんか。
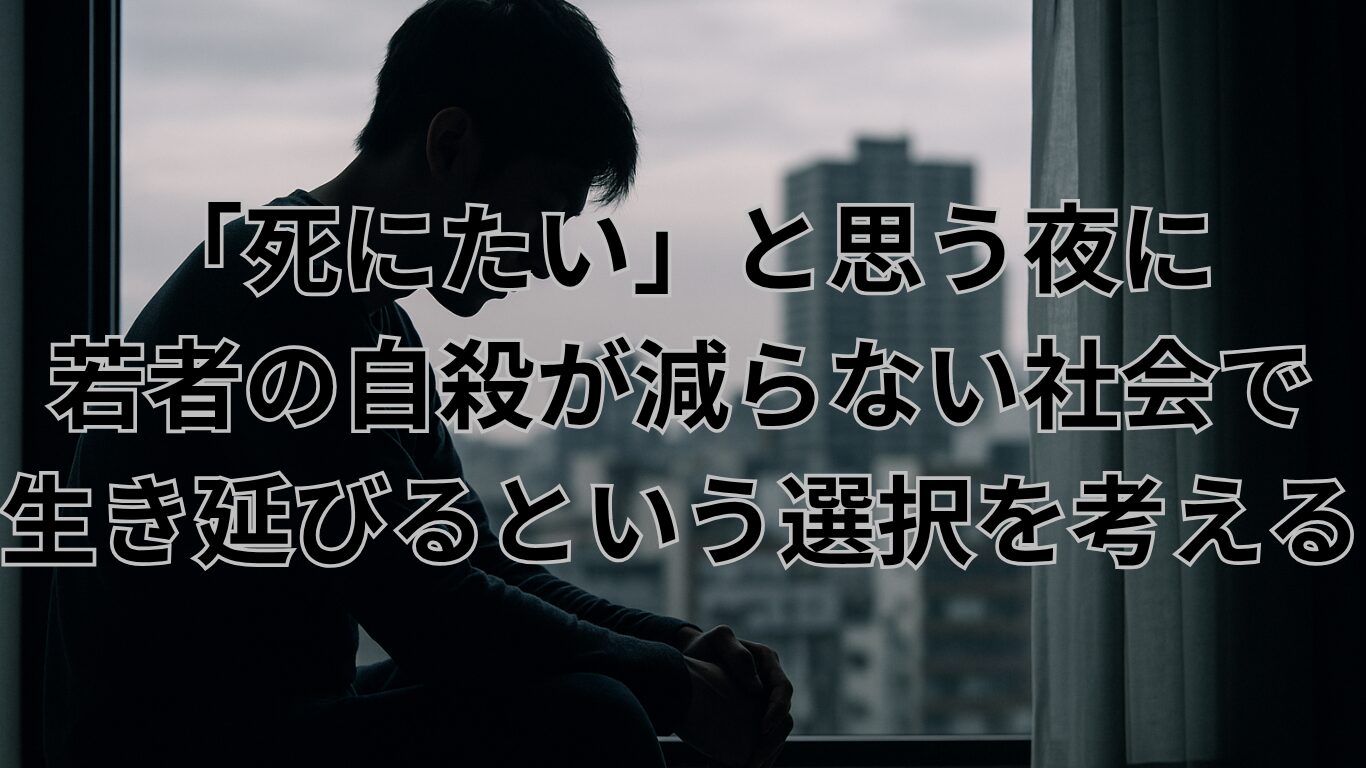

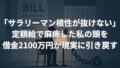
コメント