こんにちは、奨学金男です。
2025年10月21日、高市早苗さんが内閣総理大臣に就任しました。
ニュースを見て、「ついに女性首相の誕生か」と世間がざわつく中、私はひとり、部屋の中で思いました。
「この人が総理になって、私の生活はどう変わるんだろうか?」
正直に言えば、政治には詳しくありません。
それでも、2100万円を超える奨学金を背負い、毎月の返済に追われながら生きている身として、「この国の舵取りがどう変わるのか」は、どうしても気になります。
女性初の総理という希望と現実
高市内閣の誕生は、日本の政治史において大きな節目です。
女性初の総理ということで、メディアは「新しい時代の象徴」として連日報道しています。
けれど、私のように「日々の生活で精一杯」の人間にとって、それはどこか遠い話です。
ニュースの中で見る政治家たちのスーツはいつもきれいで、明るい照明の中で語られる政策は、まるで別世界の言葉のように感じてしまう。
私が知りたいのは、「この人が総理になって、生活は少しでも楽になるのか」という一点だけです。
高市さんの経歴を知って感じた「努力の物語」
自民党総裁就任のニュースを見てから、少しだけ高市さんの経歴を調べてみました。
意外だったのは、彼女自身も決して裕福な出身ではなかったということ。
苦学して大学を卒業し、政治家になった。
つまり、彼女自身も「努力して這い上がった人」なのです。
その部分だけを見ると、私は少し勇気をもらいました。
なぜなら、私も「努力すれば報われる」と信じてここまで生きてきたからです。
高校2年のときに父を亡くし、母子家庭で育ちました。
3浪してようやく私立の6年制大学に進学し、国家資格を取った。
でも、その裏には2100万円以上の借金という現実があります。
毎月、給料の多くが返済に消えていく。
同世代が旅行や結婚の話をしているとき、私はただ「返済残高」を計算している。
だからこそ、高市さんのように「苦労しても道を切り開く人」が国のトップに立ったことは、少しだけ希望でもありました。
「自己責任社会」の象徴としての高市内閣
一方で、彼女の掲げる政策やスタンスを見ていると、不安もあります。
高市さんは、これまで「自助」「努力」「成長」を強く訴えてきた政治家です。
そのため、一部では「弱者を切り捨てるのではないか」という懸念も出ています。
もちろん、自分の力でなんとかしようとする姿勢は間違っていません。
けれど、現実には「努力しても報われない人」が確実に存在します。
例えば、私のように奨学金返済で生活がギリギリな人たち。
フルタイムで働いても貯金できず、将来への不安ばかりが増える層です。
「努力が足りない」と言われれば、それまでかもしれません。
でも、努力するための時間も余裕も奪われている現実を、誰が見てくれるのか。
「弱者男性」や「貧困層」という言葉が、ネット上では揶揄の対象になる一方で、政治の場でも置き去りにされている気がします。
だから私は、高市内閣が本当に「誰のための政治」をするのかを、しっかり見届けたいと思っています。
「努力する人に報いる政治」への期待
高市氏は日本経済の「成長」や「底力」を打ち出し、国民や企業が自ら努力して高みを目指す姿勢を称える一方、現場や弱い立場の人々への緊急支援や柔軟なサポート策も同時に訴えています。
たとえば、赤字の中小企業や苦境にある農業・漁業を積極的に補助する仕組みを政策に組み込み、「努力している人や現場」に寄り添う現実主義も強調しているとのこと。
そうした姿勢に、私はある程度の期待もしています。
単なる「自己責任論」ではなく、「努力している人にチャンスを与える政治」であってほしい。
それが実現すれば、私のように苦しみながらも働き続ける層にも、希望が見えるかもしれません。
女性首相だからこそ、「女性活躍」よりも「貧困対策」を
高市さんは「機会の平等」や「全ての世代・全ての力を結集して前進する」という表現を用い、ジェンダーを強調せず、公平な競争社会を志向するメッセージを発しています。
内閣全体の基本方針としては、物価高や経済安全保障への対応を中心に据え、男女平等や女性活躍については大きなテーマとして掲げませんでした。
つまり、高市首相は形式的に「女性首相」として注目を集めつつも、「女性の地位向上」や「女性が輝く社会」といったスローガンは避け、能力主義と現実主義を重視した立場を示したのです。
私が感じるのは、「男女問わず、まずは貧困から抜け出せる社会」が必要だということ。
性別以前に、お金がない人は選択肢を持てないのです。
奨学金返済に追われる若者、非正規雇用で不安定な男性、結婚も諦めた独身層。
この国では、そういう人たちが増え続けています。
そして、彼らの声はあまりにも小さい。
もし本当に「誰もが生きやすい社会」を目指すなら、まず「経済的に苦しい人」に光を当ててほしい。
教育費の負担軽減、住宅支援、非正規からのキャリア支援。
それらこそが、少子化対策にも、社会の安定にもつながるはずです。
政治に期待しすぎない、けれど無関心ではいられない
正直、私は政治に大きな期待をしていません。
どんな政権になっても、急に給料が上がるわけでも、奨学金が帳消しになるわけでもない。
それでも、「政治に無関心でいられない理由」があります。
なぜなら、政治が決めることの積み重ねが、最終的に私たちの生活に返ってくるからです。
例えば、教育無償化や利子免除の制度が広がれば、将来の私のような若者が救われます。
逆に、社会保障が削られたり、税負担が増えたりすれば、今よりさらに苦しくなる。
だから私は、ニュースを見るたびに「どうせ変わらない」と言いながらも、つい画面を見てしまう。
それは、ほんのわずかな希望が、まだ心のどこかに残っているからだと思います。
「高市内閣の経済政策」は、私たちの生活に届くのか
発足直後の高市内閣が掲げているのは、「成長と分配の両立」。
つまり、経済を成長させながら、成果を広く国民に還元するという構想です。
ただ、この「分配」の部分が、いつも曖昧です。
企業が利益を上げても、非正規雇用や派遣社員の給料は上がらない。
中小企業にまで恩恵が届かず、結局「一部の勝ち組」だけが豊かになる。
私は、何度もそうした構図を見てきました。
アベノミクスの時代もそうでした。
「景気回復」と言われても、実際には物価だけが上がり、生活は苦しくなった。
もし今回も同じような「成長頼みの政治」であれば、また置き去りにされるのは私たちのような層です。
貧困層の「声にならない声」をどう拾うか
貧困は、単なる経済問題ではありません。
それは「孤独」と深く結びついています。
お金がない人ほど、助けを求める余裕も失っていく。
相談できる人がいなくなり、SNSで愚痴をこぼすことすら怖くなる。
私もそうでした。
返済や仕事に追われて、誰かと話す時間すらなくなり、気づけば「孤独」に慣れてしまっていた。
政治が本当にこの国を変えるなら、そうした「声にならない層」をどう救うかが鍵になると思います。
一律の給付金や短期的な支援ではなく、人と人をつなぐ仕組みこそ必要です。
「希望」は小さくても、持ち続けたい
私は今も毎月返済を続けています。
正直、終わりは見えません。
それでも、文章を書くことで自分の気持ちを整理し、同じように悩む人に何かを届けられたらと思っています。
高市内閣が発足したこの日、私の生活が劇的に変わることはありません。
でも、「この国がどこへ向かうのか」を見つめ続けることで、自分の生き方も少しずつ変わっていく気がします。
「政治なんて関係ない」と言っていた頃よりも、今の私は少しだけ現実を直視できるようになった。
そして、それはきっと「生き抜く力」にもなる。
おわりに
高市さんがどんな内閣をつくり、どんな未来を描くのか。
それをすぐに判断するのはまだ早いと思います。
ただ一つ言えるのは、どんな政権であっても、「貧困に苦しむ人を見捨てない社会」であってほしいということ。
努力できる人も、努力する余裕がない人も、等しく生きられる国であってほしい。
それが叶うなら、私はきっと、少しだけこの国を好きになれる気がします。
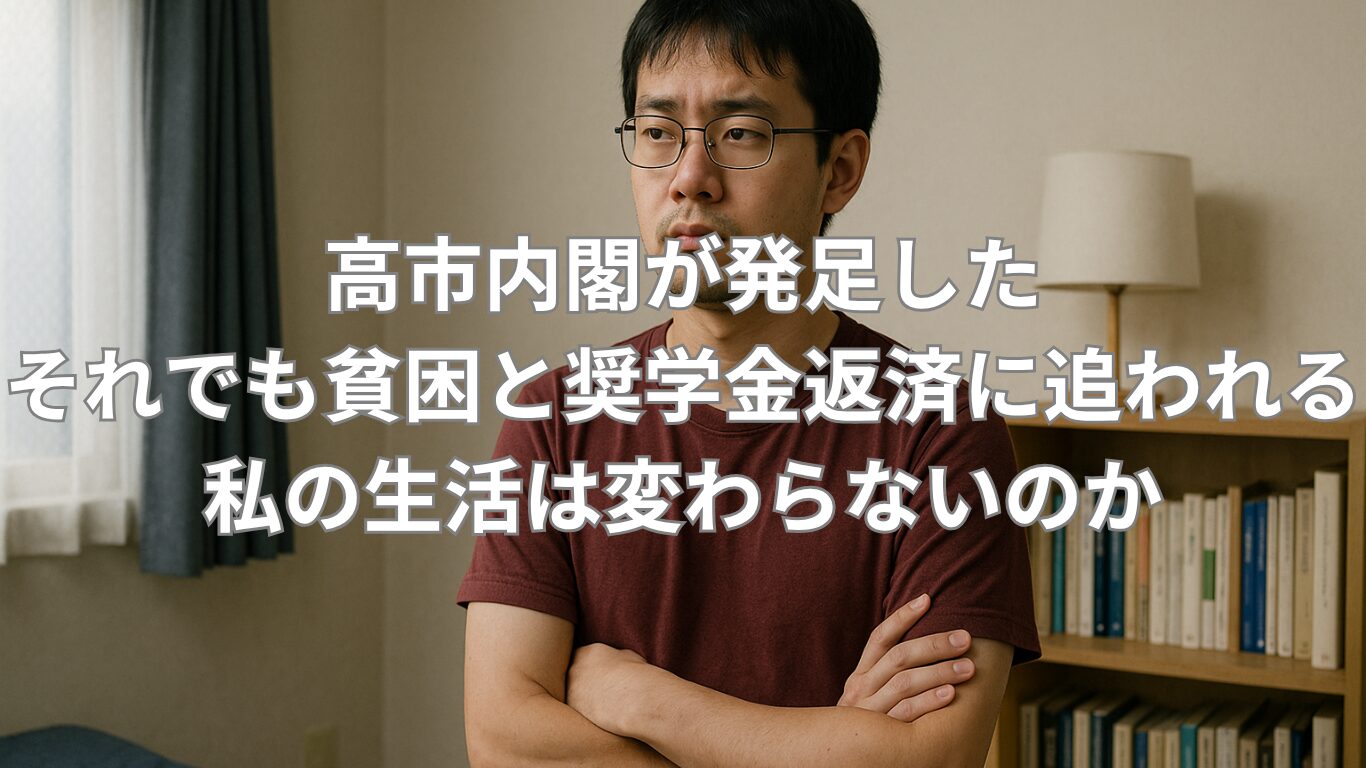
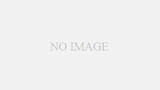

コメント