こんにちは、奨学金男です。
今日、SNSを眺めていたら「10月17日は貯蓄の日」と流れてきました。
正直、最初は「そんな日があるのか」と思いました。
でも、気になって少し調べてみると、この「貯蓄の日」は戦後の日本がまだ貧しかった時代に、「お金を大切に使おう」という意味で制定された日なんだそうです。
……そう聞くと、なんだか皮肉な気持ちになります。
だって、いまの日本もまた「お金がない」と感じている人が増えています。
物価は上がる一方、給料は上がらず、奨学金を返しながら暮らしている人間にとって、「貯蓄」なんて遠い夢のような言葉です。
「貯金ゼロ」でも責められる時代
「貯蓄の日」なんて聞くと、多くの人が「自分も貯めなきゃ」と焦ると思います。
でも、現実には貯金ゼロ世帯が過去最多だというデータがあります。
ある調査によれば、20代の単身世帯のうち、4割以上が「貯金ゼロ」。
しかも、その多くが「無駄遣いをしているわけではない」と答えています。
私もまったく同じです。
浪費しているつもりはない。
外食を減らし、服も数年単位で買い替える程度。
それでも、奨学金返済と生活費だけで、毎月がギリギリです。
それなのに、ニュースでは「若者の貯蓄意識が低い」とか「将来の備えが足りない」などと、まるで努力不足のように言われる。
でも、本当はそうじゃない。
そもそも貯める余裕がないんです。
私の「貯められなかった数年」
私は6年制の私立大学をなんとか卒業して国家資格を取りました。
学費と生活費のほとんどは奨学金。
返済総額は2100万円を超えています。
最初の就職先は基本給25万円+手当
そこから社会保険料、税金、奨学金返済を引かれると、手元に残るのは本当にわずか。
毎月の返済額は8万円弱。
これに家賃や食費、交通費を足すと、貯金に回せるお金はほぼゼロ。
ボーナスがあってようやくギリギリプラスになります。
そうやって気づけば、社会人になって数年が経ちました。
今でこそ投資もできていますが、最初は貯金らしい貯金は全然できませんでした。
「努力不足」ではなく「構造の問題」
貯金ができないのは、私が怠けているからではありません。
そして、あなたもそうではないと思います。
いまの日本社会は、「貯められない人」を量産する構造になっています。
- 非正規雇用の割合が増えている
- 物価上昇に対して賃金が追いつかない
- 奨学金という名の「借金」を背負って社会に出る
- 家賃・光熱費・保険料など固定費が年々上昇
これらが積み重なれば、どんなに節約しても「貯める」というステージに到達できないのです。
それでも、多くの人は「自分の努力が足りない」と自分を責めます。
でも、私は声を大にして言いたい。
「貯金ができないことは、あなたのせいじゃない」
貯蓄を「数字」ではなく「心の余裕」として考える
最近になって、私は「貯蓄」という言葉の意味を少し変えて考えるようになりました。
昔の私は、「貯金額=価値」だと思っていました。
通帳に残高が少ないと、自分の人生まで失敗しているように感じていた。
でも、奨学金を返し続けるうちに、気づいたんです。
お金は「心の余裕をつくるための道具」にすぎないと。
もし今月、1万円でも余裕があるなら、
それを「無駄遣い」と考えるのではなく、自分を少し楽にする費用だと思えばいい。
たとえば、
- たまにはデザートを買って疲れを癒す
- 1冊の本を買って気持ちを立て直す
- 電車を使ってでも気分転換の散歩に出る
そうした「小さな自分への投資」が、長期的にはメンタルの貯金になります。
「貯める」よりも「減らさない」工夫を
2100万円の借金を抱えて生きていると、否応なしに「お金に敏感」になります。
でも、私はもう“無理に貯めよう”とは思っていません。
代わりに意識しているのは、「減らさない」こと。
- 不必要なサブスクを解約する
- 携帯プランを見直す
- 格安のネット保険を選ぶ
- ポイントやキャッシュレス還元を活用する
こうした地味な工夫の積み重ねが、結果的に「貯金」と同じ効果を生みます。
そしてなにより、「浪費していない自分を認めること」。
これも、立派な節約です。
「お金を貯めること」がゴールではない
私が20代のころ、「30代までに100万円貯めたい」と思っていました。
でも現実は、貯めるどころか奨学金の返済に追われ、貯金通帳の数字はほとんど変わらなかった。
けれど、30歳を超えて思うのは、
「お金を貯めること」よりも「心をすり減らさずに生きること」のほうがずっと大事だということ。
お金は生きるための手段。
貯めること自体が目的になってしまうと、かえって苦しくなります。
貯蓄の日に改めて感じたのは、
「お金に支配されない生き方」こそ、本当の貯蓄」ではないか、ということです。
「貯蓄の日」が教えてくれたこと
お金を貯めることができない自分を、昔は恥ずかしく思っていました。
同世代の友人が「つみたてNISA」や「iDeCo」の話をしているのを聞くと、
「自分は社会人失格なんじゃないか」とさえ感じたこともあります。
でも今は、少しだけ違う考えを持てるようになりました。
「貯蓄の日」は、“貯められる人”のための日ではなく、
“お金の現実に向き合う人”のための日でもある。
借金を返しながら生きる私たちにとっても、この日は意味がある。
お金がなくても、人生は終わらない。
たとえ貯蓄がゼロでも、あなたの価値はゼロじゃない。
さいごに:貧困の中でも希望を持てる理由
お金の不安は、人生の不安と直結します。
でも、お金がないからといって、希望まで失う必要はない。
私は今でも奨学金を返し続けています。
2100万円という金額を聞くと、多くの人が驚きます。
でも、返済を続けるたびに感じるのは、「終わりに近づいている」という事実です。
少しずつでも前に進んでいる。
それが、私にとっての「精神的な貯蓄」なんです。
「貯蓄の日」に、無理にお金を貯めようとする必要はありません。
それよりも、自分の努力や現実を受け入れること。
それが、この時代に生きる私たちにとっての“新しい貯蓄”だと思います。
まとめ
- 「貯金できない」のは努力不足ではなく、社会構造の問題も大きい
- 小さな節約や「減らさない工夫」も立派な貯蓄
- 精神の余裕=心の貯金を大切に
- 貯蓄の日は、“お金に向き合うきっかけ”であればいい
お金がない人間が「貯蓄の日」を語るなんて、少し滑稽かもしれません。
でも、私は声を大にして言いたい。
貯められなくても、
生きていく価値はある。
それこそが、今の日本に必要な「貯蓄」なのかもしれません。
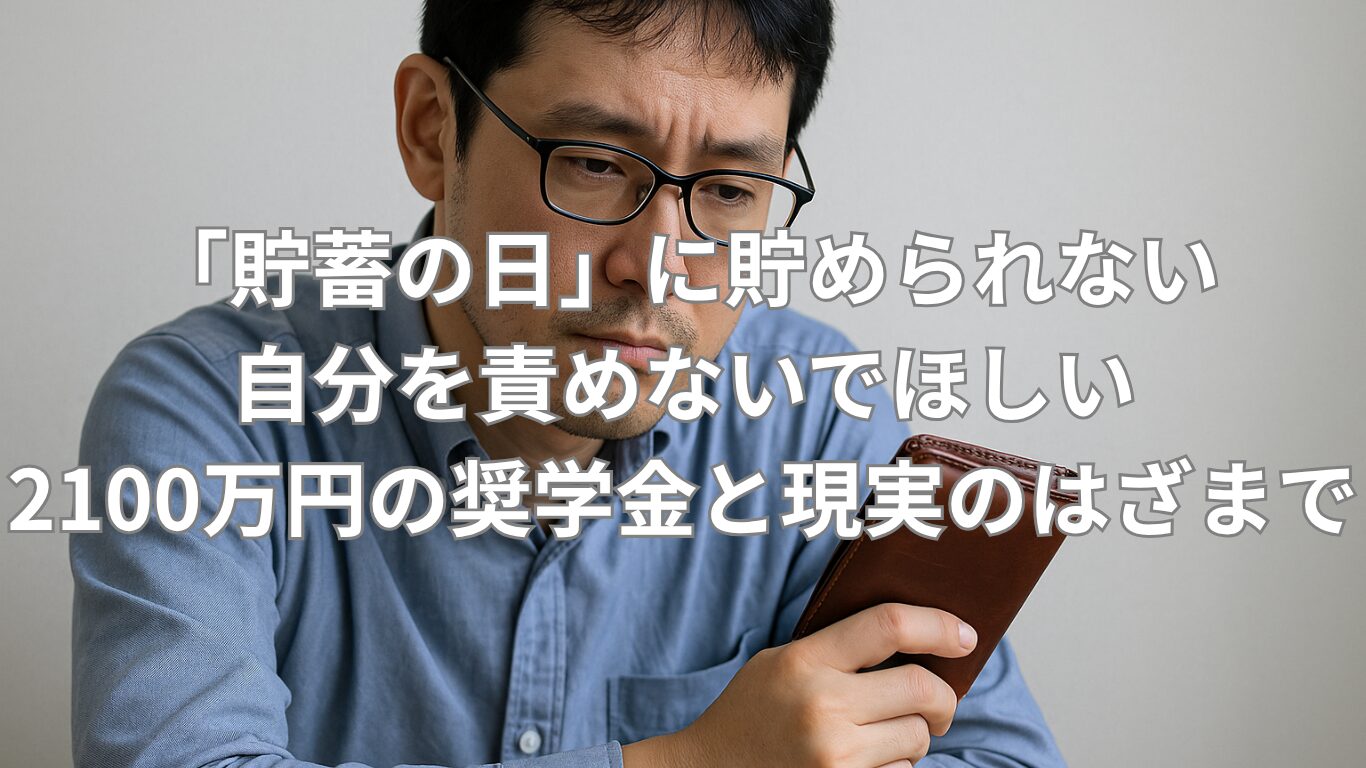

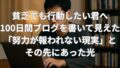
コメント