こんにちは、奨学金男です。
私は奨学金総額2100万円を背負って生きています。高校2年のときに父を亡くし、母子家庭で育ちました。3浪の末にようやく6年制の私立大学に進学し、国家資格を取りました。
私についてはこちらの記事を読んでください。
表面上は「資格職で安定している人間」かもしれません。でも、現実は違います。月々の返済、生活費、税金、そして将来の不安――「弱者男性」としての現実に、日々押しつぶされそうになることがあります。
今日は、そんな私の生活の中で、ふと気づいた「無駄」について話します。
テーマは――『テレビを見ないのにテレビが家にある』という話です。
テレビを買ったのは「大学生のとき」
私がテレビを買ったのは、大学入学のとき。
実家ではテレビがあるのが当たり前の生活をしており、一人暮らしになって、テレビを買うのになにも疑問は持ちませんでした。
大学に通い、部屋にテレビがあり、夜はバラエティー番組を見ながらご飯を食べる――そんな“普通の生活”。
父を亡くしてから「普通」がどれだけ尊いかを痛感していた私は、無意識にその「普通」にすがりたかったのかもしれません。
実際にテレビを買ってみると、最初の頃はよく見ていました。お笑い番組、ニュース、バラエティ。
けれども、いつの間にかつけなくなりました。勉強が忙しかったし、静かな方が集中できたからです。
社会人になっても「テレビは部屋の片隅に」
就職して一人暮らしを続けるようになって、テレビはそのまま部屋にあります。
ただのインテリアになり果てているのに、なぜか手放せない。
画面にはいつも埃が積もり、リモコンの電池は切れたままです。
一方で、私のスマホはフル稼働。ニュースもYouTubeもSNSも全部スマホで済む時代。
正直、テレビをつける理由が見当たりません。
でも、「テレビがある」という事実だけでNHKの受信料を払わなければならない。
NHK受信料という“無意識の固定費”
私は今、NHKの受信料を毎月ちゃんと払っています。
見てもいない番組にお金を払うという矛盾。
まるで「見ていないのにNetflixのサブスクだけ継続してる」ようなものです。
それでも解約できないのは、「面倒だから」――この一言に尽きます。
NHKの解約方法すら調べていません。
しかも、平日は仕事で忙しく、休日は疲れて寝て終わる。
「いつかやろう」と思いながら、気づけば数年が経っていました。
それでも、受信料がカードから引かれるたびに「これって本当に必要なのか?」と自問します。
奨学金を返済している身としては、たとえ月数千円でも節約できるなら節約したい。
けれども、その数千円を削るだけの「行動エネルギー」がない。
ここに、現代の貧困と弱者男性の現実があると感じます。
行動できないのは「怠け」ではなく「エネルギー切れ」
「見ていないなら解約すればいいじゃん」と言う人もいるでしょう。
確かに正論です。でも、それができないのが現実です。
朝はギリギリまで寝て、仕事はわんこそばのようにどんどん舞い込んでくる。
夜は残業、帰宅してコンビニ弁当を食べて寝る。
翌朝にはまた同じ日常が始まる。
人間は、生活がギリギリになると合理的な判断ができなくなります。
心理学的にも「貧困による認知的負荷(cognitive load)」と呼ばれる現象があります。
簡単に言えば、「お金や将来の不安で頭がいっぱいになり、他のことに頭が回らなくなる」状態です。
私はまさにその典型です。
奨学金の返済、老後の不安、結婚できる気配のない人生。
そんな中で「NHKを解約しよう」と思っても、
「今じゃなくてもいいか」と先延ばしにしてしまう。
「貧困」と「弱者男性」の共通点は“諦めの学習”
心理学用語で「学習性無力感(learned helplessness)」という言葉があります。
努力しても報われなかった経験を重ねるうちに、「どうせ何をやっても変わらない」と感じるようになる現象です。
私にとって、それがまさに今の生活。
節約をしても、返済総額はビクともしない。
頑張って働いても、物価は上がり、手取りは増えない。
そんな中で「テレビを処分する」「NHKを解約する」という小さな行動ですら、
どこかで「やったところで人生は変わらない」と思ってしまう。
これが“弱者男性”の現実なんです。
「テレビがある」だけで見透かされる貧困の構造
面白いことに、テレビって「豊かさの象徴」だった時代もありました。
昭和のころは「三種の神器」と呼ばれ、テレビを持っている=中流の証だった。
でも、令和の今、テレビを持っていることは「時代遅れ」や「無駄の象徴」になりつつあります。
にもかかわらず、私のような“脱弱者男性”を目指す人間が、
その無駄を抱えたまま生活している。
これは単なる個人の怠慢ではなく、社会構造的な「罠」だと思います。
つまり、貧困層ほど固定費の削減に手が回らない。
情報のアップデートも遅れがちになる。
結果として、無駄な支出を続け、ますます貧困が固定化していく。
「テレビを処分する」という行動ができたら、人生は少し変わる
ある日、私は思いました。
「もしこのテレビを処分できたら、自分は少し変われるんじゃないか」と。
テレビを手放すことは、単なる節約ではなく、
“行動できない自分”を断ち切る第一歩なのかもしれません。
とはいえ、実際に処分しようとすると面倒です。まずは処分の仕方を調べないといけない。
それでも、こうして記事に書くことで、少しずつ意識が変わってきました。
行動できない理由を「怠け」で片づけるのは簡単です。
でも、その裏には、エネルギーを削り取られる日常がある。
私はその現実を言葉にしていきたい。
「行動しない罪悪感」をエネルギーに変える
私はいま、「行動できない自分」を責めないようにしています。
なぜなら、それもまた現実の一部だからです。
だけど、「いつかやる」と言い続けるだけでは、何も変わらない。
だから、こうしてブログを書いています。
同じように奨学金や貧困、孤独に悩む人たちへ、
「こんなふうに悩んでるのは自分だけじゃない」と伝えたくて。
テレビを処分するかどうかは、小さなことかもしれません。
でも、その小さな一歩が、自分の人生を取り戻す最初のアクションになる気がします。
終わりに:弱者でも、生きる意味はある
私は身長168cm、独身、そして2100万円の奨学金を背負った「弱者男性」です。
だけど、こうして文章を書けるだけの心の余裕は、まだ残っています。
もしかしたら、このブログを読んでいるあなたも、
テレビのように「見ていないのに置いたままのもの」を抱えていませんか?
それが人間関係でも、モノでも、過去の夢でも――
手放すことで、少しだけ軽くなるかもしれません。
私も、この週末こそ、テレビを処分しようと思います。
たぶん、また疲れて寝て終わるかもしれないけれど。
それでも、「変わりたい」と思えるうちは、まだ終わっていない。
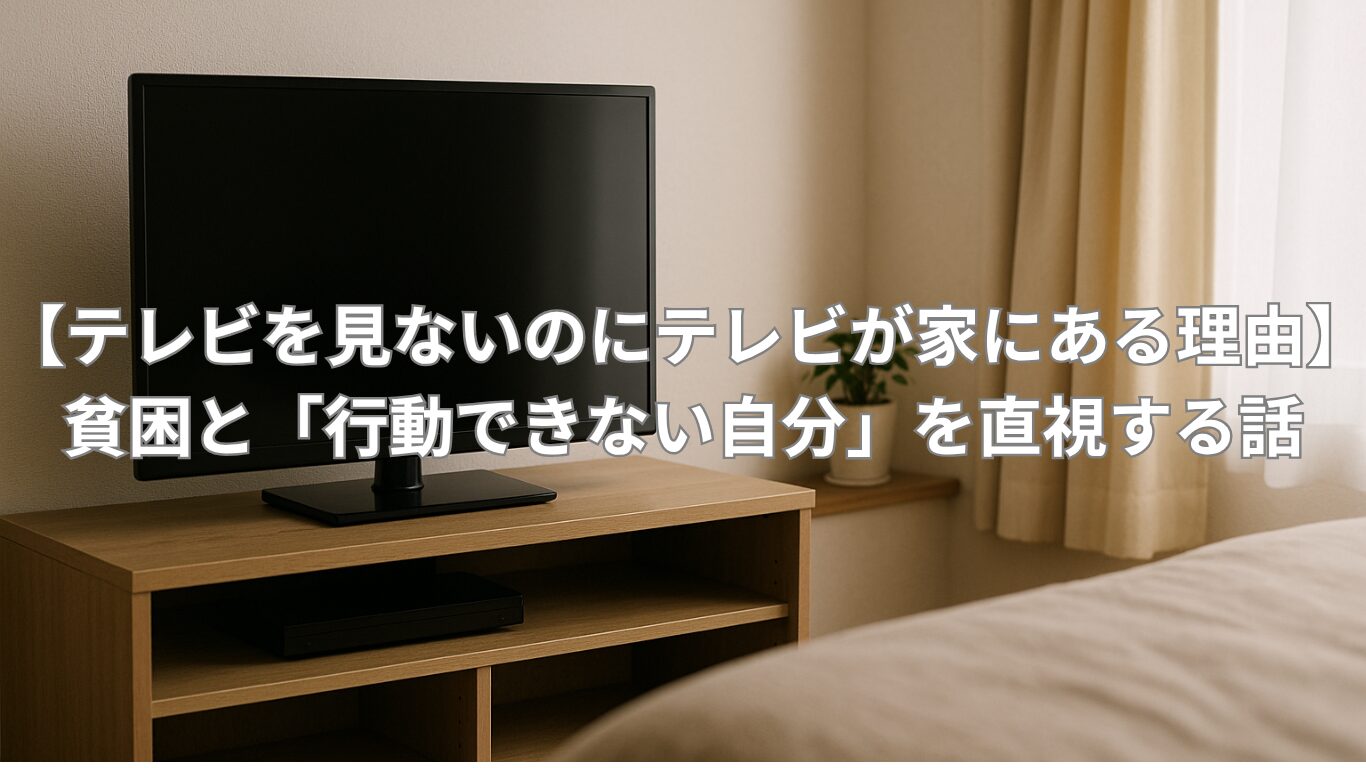
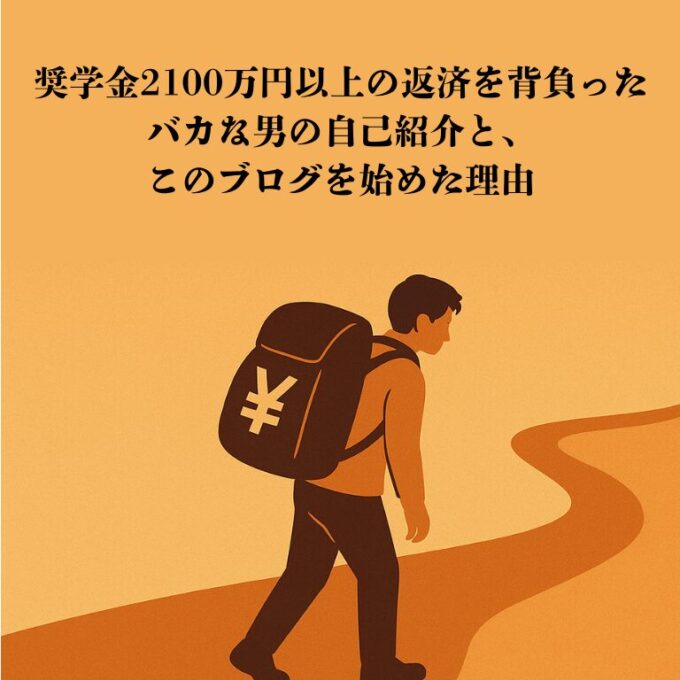


コメント