2025年7月17日、TBS「news23」でクイズ王・伊沢拓司さんが語った一言が、ずっと心に残っている。
「保守風の政党が増えている中で、“わかりやすさ”に騙されないよう警戒した方がいい。苦しみながら投票してほしい。」
「苦しみながら投票してほしい」という言葉。
それは、奨学金2100万円の返済をしながら生きる自分のような人間にも向けられたものだと感じた。
■ 私の背景:奨学金2100万円を背負って
私自身は高校2年生のときに父を亡くし、以来母子家庭で育った。
そこから3浪してようやく6年制大学に入り、国家資格を取得し、今は社会人として働きながら奨学金を返している。
進学に必要だった奨学金の返済額は総額2100万円。
家賃・光熱費・食費に加えて、毎月の返済。
正直、贅沢なんてできるわけがない。
もちろん、自分で借りたものは自分で返す。
それは責任として受け止めているし、繰り上げ返済は無理なので、ゆっくり時間をかけながら返している。
しかし――
この「奨学金ありきの進学」という構造を、次の世代にまで押し付けていいのか。
そこには、大きな疑問がある。
■ 「子どもの貧困対策法」から10年以上。現実は変わったのか?
2013年、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定された。
この法律は、子どもが生まれ育った家庭の経済状況によって、教育や将来に格差が生じないようにすることを目的としている。
制定から10年以上が経った今、果たして現実はどこまで変わっただろうか?
統計上、確かに「子どもの貧困率」は一時期よりは低下したとされている。
しかし、現場レベルではまだまだ根深い格差が残っている。
- 奨学金に頼らざるを得ない高校生・大学生が依然として多い
- 進学をあきらめざるを得ない子どもたちも存在する
- 給付型奨学金の対象は限定的
「制度はある、けれど届かない」
この現実が、10年経ってもなお変わっていないのだ。
■ 借金でしか進学できない現実|18歳は“成人”だけれど
2022年から、日本では「18歳成人」がスタートした。
それによって、奨学金の申込や契約に関しては、成人(18歳以上)であれば法律的な契約を自分ひとりで結ぶことが可能になったようだ。
つまり、18歳の時点で親の同意なく、奨学金を借りるための契約を自分自身の責任で行える。
ただし、奨学金の審査には世帯収入の証明などで保護者の協力が必要なことはある。
つまり「契約自体」は親の同意なしで実行できる(と私は思っているけど、間違っていたらすみません)。
しかし、私はこの変化を必ずしも「進歩」だとは思っていない。
法律上の成人といっても、18歳の時点で数百万円の借金が、将来にどれほどの重圧となるかを理解できる人はどれだけいるだろうか?
18歳に生活をしながら数百万円を返済する大変さがわかるだろうか。私が18 歳の時は全くわからなかった。
私自身、当時は「奨学金を借りて進学するのが当たり前」「大学に行かないと人生が詰む」と思い込んでいた。
その背景には、周りはみんな進学するという環境と情報不足があった。
奨学金制度が「救済」ではなく、「分断」を生み出している――
それに気づいたのは、大学生になって貧困の子どもたちとかかわる機会があったからだ。
この話はまたいつかどこかでしたいと思う。
■ 参院選と、貧困の連鎖を断ち切る視点
今回の参院選で各政党が掲げている政策の中には、「教育無償化」「消費税減税」「手取りアップ」などのキーワードが多く見られるようになった。
だが、既に借りてしまった社会人や、進学そのものを諦めた“隠れ貧困層、奨学金を借りたが退学して借金だけが残った人に支援が行き届くのか疑問に思った。
自分自身がその“届かない側”だからこそ、少しでも救われる人が増える政策が実現してほしい。
■ 自分が投票する理由|次の世代に同じ負担を背負わせないために
私が本当に願っているのは、未来ある子どもたちが、「借金しなくても進学できる社会」だ。
繰り返すが、私は借りたものを返すつもりだ。
けれど、「自分は借りたんだから、あなたたちも頑張って返しなさい」とは、絶対に言いたくない。
私は、今の自分の苦しさを、次の世代に繰り返してほしくない。
特に、経済的に困難な家庭の子どもが「お金が理由で学ぶことを諦める」ことがあってはならない。
それを実現するためには、個人の努力では限界がある。
だからこそ、私たちが投票しなければ、この不公平はずっと変わらないまま残る。
■ まとめ|苦しみながらでも、投票する
奨学金の返済、日々の家計、将来への不安、結婚できるかどうかすら分からない生活。
そんな中で、「投票する意味があるのか」と迷う気持ちもよく分かる。
けれど、声を上げない限り、変わることは絶対にない。
政治は、何もしなければ、今のままを選び続ける。
むしろ現状が悪化していくかもしれない。
私たちが“苦しみながら”でも投票することでしか、貧困の再生産を止めることはできないのだ。
私がこうして文章を書いているのも、同じような苦しみを抱える誰かが、「自分だけじゃない」と思えるようにするためだ。
奨学金の返済で苦しんでいる人。
子どもの将来に不安を抱えている親御さん。
教育の機会に恵まれなかった人。
「生まれ」で人生が決まることに悔しさを感じている人。
私は、あなたのことを“他人事”だと思わない。
私自身がそうだったからこそ、あなたにも伝えたい。
選挙のたびに失望しているあなたへ。
今回も諦めずに、投票してみませんか?
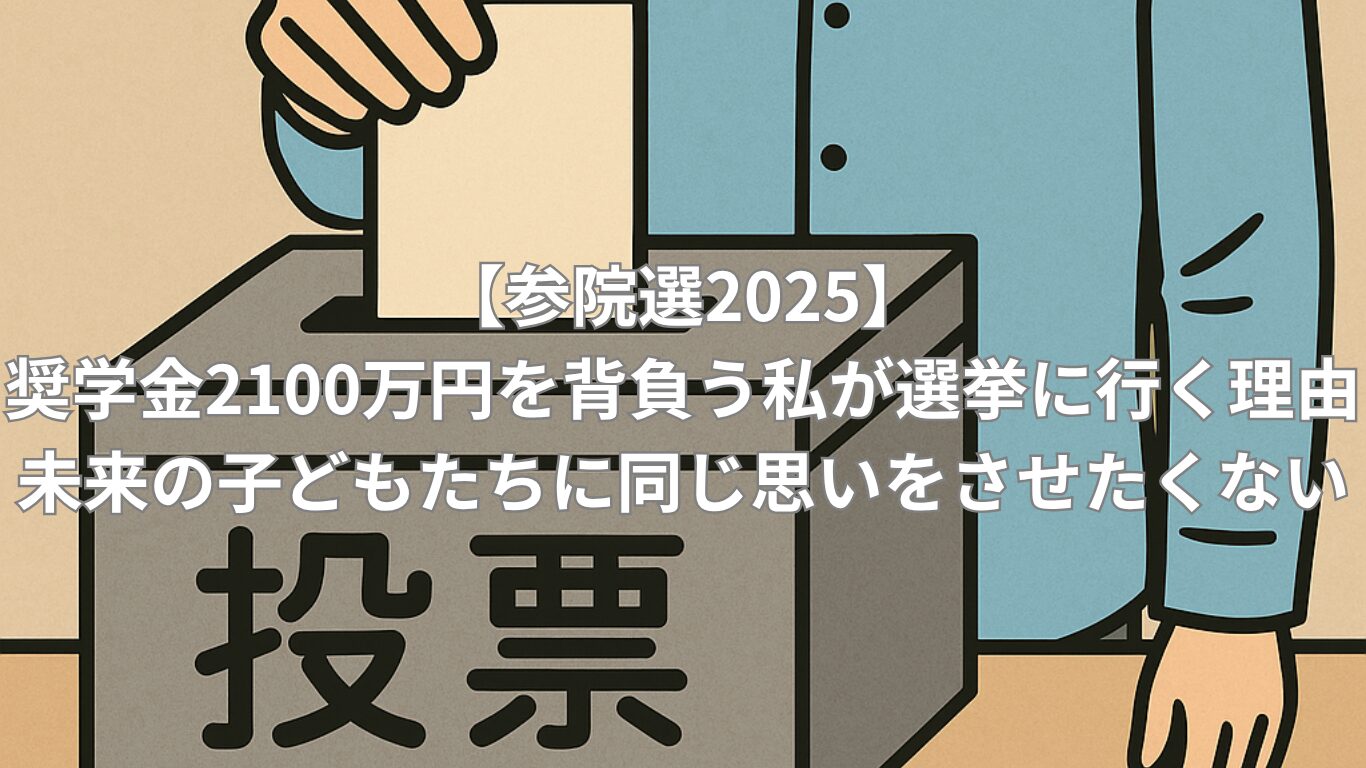
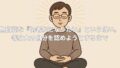

コメント