こんにちは、奨学金男です。
先日、Yahoo!ニュースで「大学授業料無償化に“3浪の壁”」という記事を見ました。
要約すると、「大学授業料を国が支援する制度において、3浪以上していると無償化の対象外となる」というルールがあり、それが若者の挑戦機会を奪っている、という指摘です。
私自身、高校卒業後に浪人を重ね、経済的に苦しみながら大学進学と奨学金の道を選んだ者として、この“3浪の壁”という制度には、他人事ではない怒りと危機感を覚えます。
本記事では、
- なぜ“3浪の壁”が制度上残っているのか
- それが私やあなたのような弱者男性・貧困層にどう響くか
- 私の体験から見えるリスクと対策
- これから借りようとする人/返済に悩む人に向けたメッセージ
を、私の人生も交えて語りたいと思います。
1.“3浪の壁”とは何か?制度のおかしな制限
この記事で指摘されている制度の内容を整理すると、以下のような点があります。
- 授業料無償化制度は、入学金と授業料を国が支援する制度で、教育費の軽減と少子化対策を目的としています。
- 制度改正により、多子世帯なら所得制限が緩和され、適用対象が拡大されたという事情もあります。
- ただし、制度には「高校卒業から翌年度の末日から大学入学日まで2年を経過していない者」が対象、という規定があるようで、これが“浪人年数”の制限につながっている。
- 結果として、3浪以上すると、制度の恩恵(授業料無償化支援)を受けられないケースがある、という点が問題視されています。
これを「3浪の壁」と多くの人が呼んでいます。
この制限の意図は、ある意味で「無限に浪人できるのは制度として無駄が生じやすい」「ある程度の線引きは必要」という考え方に根ざしているのでしょう。しかし、現実にはその線引きが、人生の可能性を、特に経済的に余裕のない人たちの前で閉ざしてしまうリスクを孕んでいます。
特に、浪人したい—しかし 家計が苦しい、予備校・塾にかけられる予算が限られている、という若者にとって、“3浪以上は制度対象外”という制限は、挑戦の意欲をそぎ、諦めを強いる壁となる可能性があります。
制度の“公平性”を語るなら、「挑戦の回数」に制限を設けるのであれば、それを支える受験指導・進学支援を強化すべきところを、形だけの制限にとどめてしまえば、本来救われるべき人たちを切り捨てる構図が生まれてしまいます。
2.“3浪の壁”はなぜ問題か — 私の経験を振り返って
私のバックグラウンドをあらためてお伝えすると:
- 高校2年生のときに父が亡くなり、母子家庭で育ちました。
- 大学へは3浪を経て進学しました(浪人生時代をひとつずつ積み重ねていった)。
- 私立の6年制大学で学び、最終的に国家資格を取得しました。
- 現在、奨学金の返済総額は 2100万円以上 にのぼります。
この人生を振り返ると、もし“3浪以上”を制度上制約されていたら、私の選択肢は大きく狭まっていたでしょう。以下、私の体験に即して、なぜこの制度が危ういかを語ります。
2‑1. 浪人という選択は「ラストリゾート」であった
私は、現役合格できなかった時点で、「浪人してでも大学に行く道」を選びました。周囲には「働いて金をためて大学に行く」という選択を取る人もいましたが、私はどうしても学びを断ち切りたくなかった。
浪人するにあたって、予備校代や模試代、参考書代、生活費……すべてを教育ローンと親に負担してもらいながら、毎年ギリギリの状態で勉強を続けました。友人が進学していく中、孤立感と焦燥を抱えながらの3浪でした。
もし制度上、3浪までなら支援対象として認めない、を明確にされていたら、私は2浪で諦めざるを得なかったかもしれません。あるいは、もっと低レベルの大学・学部に妥協せざるを得なかったかもしれません。
2‑2. 経済的ハードルが挑戦を阻む
浪人生時代、家計は火の車でした。母子家庭だったため、私が浪人中に親から大きな支援を受けることは困難でした。本来であればアルバイトを掛け持ちしながら勉強し、受験料や予備校費用を捻出するのでしょうが、頭の悪い私は勉強をするだけで精一杯でした。
そのため、浪人できる年数には限界がありました。体力・金銭・精神、すべてをギリギリで維持していたので、3浪を超える挑戦は肉体的にも精神的にも破綻するリスクが高かったのです。
制度が「3浪未満なら支援対象」というルールを持っているなら、実質的には「2浪までしか実行可能な挑戦」が許されている、ということと同義です。逆に言えば、3浪以上の挑戦意欲ある受験生を切り捨てている制度運用になっている可能性すらあります。
2‑3. 精神的に砕かれる“制度に縛られる挑戦者”
私が浪人生だった頃、しばしば思ったのは「制度って、誰のためにあるのだろう?」ということです。向こう側が、どこまで受験生の苦境を想像して制度を設計しているのか、という疑問。無償化支援でも、「制度の枠組み」が無意識の足かせになっていることがある。
もし私が「3浪以上=支援対象外」の制度と向き合っていたら、自らの挑戦に縛りを感じ、自分を律することができなかったかもしれません。「あと1年、もしダメならあきらめよう……」という萎縮が常に自分の中に生まれたはずです。
実際、浪人中は焦りとの戦いでした。周囲の浪人生を見て「自分は本気なのか?」と自問し続け、時には心が折れそうになる年もありました。
そして、その年数制限が、結果的に「挑戦から降りる言い訳」を制度の側に与えてしまうことになるのではないか、という恐れも感じます。
3.“3浪の壁”は弱者男性・貧困層にどう響くか
私の体験を踏まえたうえで、以下のように考えます。
3‑1. 出発点の不利をさらにつける制限
貧困層、片親家庭、母子家庭、低所得層……こうした環境にある人たちは、最初から受験・進学の出発点で多くの不利を抱えています。塾・予備校、参考書、模試、受験料、交通費、滞納しない生活維持など、すべてのコストが重くのしかかります。
そうした人たちが浪人を重ねると、経済的・心理的に追い詰められやすく、挑戦を続けること自体がリスクとなります。制度が「3浪までOK」という線引きをしているとすれば、その線引きは、最初から余力のある人にしか手が届かない余裕を与えているとも言えます。
つまり、「挑戦できる人とできない人」が制度的に固定化される恐れがあります。
3‑2. 精神的圧力とあきらめの誘導
制度の制限がはっきりあると、挑戦者はその枠内で意識的/無意識的にリスクを計算します。「3浪以上だと支援が効かないなら、2浪で勝負をかけよう」「仮に3浪目で失敗したら、もう諦めるしかない」……という発想が生まれやすくなります。
こうした思考の前提が、若者に“挑戦の萎え”を生み、早期撤退を促す力を制度自体が持ってしまうのです。
3‑3. 選択肢を狭める“妥協進学”の増加
3浪以上を支援対象から外す制度があるとすれば、挑戦余地を失った受験生は「安全策」に走りやすくなります。より低偏差値・学費の安い大学、あるいは中断・専門学校・就職という道を選ばざるを得ない。
この選択が、将来の収入・キャリアポテンシャルに影響を与え、結果的に社会的格差をさらに広げる悪循環を生みかねません。
3‑4. 性差・性別観点での構造的影響
ここで、私が“弱者男性”という立場であることを思うと、制度設計は性別・社会構造の無自覚な前提を含む可能性があります。
社会的には、男性には「稼ぐ責任」「家族を支える責任」が期待されがちです。しかし、経済的不利な中で進学・返済という重荷を負う男性だってたくさんいます。
女性に比べて、男性は「弱さを見せづらい」「頼みにくい」「相談しにくい」文化的ハードルもあります。制度的差別がないように設計されていても、運用・現実には「男性進学者・返済者」が孤立しやすい土壌があると感じます。
“3浪の壁”という制度上の制限は、挑戦者を形式上ふるい落とすだけでなく、制度と文化の交差点で、多様な弱者をさらに分断する力を持っているように思います。
4.制度の代替案・改善案を考える
では、どうすればこの“3浪の壁”の問題を軽減し、より公平な支援制度を実現できるのでしょうか。制度設計・運用の面から、いくつかアイデアを挙げます。
| 提案 | 内容 | メリット | 課題・懸念 |
|---|---|---|---|
| 浪人数制限を撤廃 or 緩和 | 3浪以上でも支援対象とする、あるいは4浪・5浪まで許可 | 真に挑戦する意欲ある学生を切り捨てない制度 | 支援の予算配分/制度の濫用防止策が必要 |
| 成績・志望理由をふまえた個別認定方式 | 浪人数だけで線引きするのではなく、模試成績・志望理由書・家庭事情を総合評価 | 一律制限の不公平さを緩和できる | 手続き・審査コストが高くなる |
| 浪人期間中支援制度(生活費・教材費補助) | 浪人中にも最低限の支援を与え、挑戦を継続しやすくする | 挑戦の継続性を支える安全網になる | 心理的依存/制度の濫用リスクの管理 |
| “挑戦期間延長オプション”制度 | たとえば「最大3浪+事情認定」で4浪目以降は特例扱いにできる制度 | 柔軟性を制度上持たせられる | 審査基準の曖昧さ・運用の恣意性リスク |
| 給付型奨学金や成績連動支援の拡充 | 支援の一部を返済不要の給付型にする、あるいは成績優秀者を優遇 | 返済負担を軽くでき、挑戦意欲を促す | 財源確保と公平な配分設計が不可欠 |
私は個人的には、「浪人数制限の撤廃 or 緩和」と「個別認定方式」の組み合わせがもっとも現実的で効果的ではないかと思います。
特に、浪人数だけで判定する制度設計は、一見平等を装っていても、最も挑戦が必要な人を制度の外に追いやる「構造的排除」になりかねません。
5.奨学金返済2100万円の私が思う“支払能力”と“制度の期待値”
本ブログのテーマである「奨学金返済」「弱者男性」「貧困からの脱却」を常に念頭に置くなら、無償化制度だけを論じて終わるわけにはいきません。最終的には「いかに返済を持続可能にするか」が鍵だからです。
私が2100万円以上の奨学金を抱えた立場から言えることは、次のような現実と期待値です。
5‑1. 返済計画は「最悪想定」で設計すべき
収入が突発で落ち込む可能性、病気・失業・家族の事情など、複数のリスクを前提に、余裕を持った返済計画を立てるべきです。最も厳しい事態でも返済を破綻させない保険的設計が重要です。
実際、私は返済計画を当初から “最悪でも支払えるキャッシュフロー余力” を基準に設定しました。無理な返済を積み上げてしまうと、挫折感・借金地獄に陥るリスクが高まります。
5‑2. 副収入・キャッシュフォローを持つ
通常のサラリーマン収入だけでは、奨学金の重さを支えきれないと感じた時期もありました。私はスキルを蓄えて副業を始め、収入源を複数化することでリスクを分散しました。
これは返済途中での「収入ショック」に対するバッファになるからです。
5‑3. 借りすぎない勇気
制度がいくら支援的であっても、借りすぎは命取りになります。支援対象だからといって、無制限に借りていいわけではありません。大学選び・学部選び・授業料・生活費見積もり・将来収入可能性まで、すべてを慎重に見通すべきです。
私は大学を選ぶとき、学費水準・就職可能性・奨学金返済のシミュレーションを重視し、借入最小化を意識しました。
5‑4. 情報発信とネットワークの構築
返済者同士の情報交換、制度変更情報のキャッチ、返済支援制度(返還猶予・所得連動返済など)のアンテナを張ることが、長期返済を乗り切る鍵となります。孤立して返済を抱え込むと、心理的な負荷が重くなります。
私は返済関連の情報を日常的に集め、自分のブログでも共有することで、自分自身の返済意識を保ちつつ、同じ境遇の人に役立てたいと思っています。
6.これから奨学金を借りようとする人、返済に苦しむ人へのメッセージ
最後に、あなたがこのブログを読んでいるということは、下記のどちらか、あるいは両方の立場かもしれません:
- これから奨学金を借りようとしている
- 今まさに返済に悩み、苦しんでいる
私からのメッセージは次の通りです。
6‑1. 奨学金を借りようとする人へ
- 借りる前に将来設計を立てよ
大学選び、学費、生活費、卒業後の収入見通しをシミュレートして、最悪ケースでも返せる水準に抑えること。 - 返済能力を超える借入は命取りになる
制度に甘えすぎず、必要最小限の借入を旨とすべき。 - 情報を武器にせよ
給付型奨学金、返済猶予制度、学費免除制度など、制度には抜け道や救済措置も存在する。関心を持って調べよ。 - 挑戦は“合理的な挑戦”を心がけよ
浪人したいなら、浪人数制限や自分の経済基盤を踏まえて、リスクを最小化するプランで挑戦せよ。
6‑2. 返済に苦しむあなたへ
- 返済計画の見直しを躊躇しないで
延滞・滞納リスクを抱えるより、借り換え、返済猶予、所得連動返済など制度を活用しよう。 - 支出の見直し+収入の分散化を図れ
家計の無駄を洗い出し、可能な範囲で副収入を確保する。小さな収入重視でも構わない。 - 同じ境遇の人との情報ネットワークを作れ
孤独に苦しまないで、返済経験者・支援団体・制度利用者とつながろう。ブログやSNS、返済コミュニティを活用。 - メンタルを保つことを最重視せよ
返済の重圧は精神を削る。心身ともに無理をしすぎず、相談・休息も取り入れながら続けていくこと。
おわりに:私はこの壁を壊したい
今回の“3浪の壁”問題の記事をきっかけに、私は改めて思いました。制度は、形だけの公平性を掲げながら、無自覚に挑戦者を排除する構造を内包しやすい。
私の人生は、挑戦と挫折の連続でした。浪人して、奨学金を抱えながら学び、返済の泥沼に足を突っ込み、なお這い上がろうともがきながら、今にいたります。
私がこのブログで伝えたいのは、「あなたの挑戦を無駄にしないために考えること」「制度に飲み込まれない知識武装」「返済可能性を見据えた計画性」です。
“3浪の壁”という制度仕様が、挑戦の芽を摘むものであってはならない。制度の枠の中であれ、枠を超える新たな道を模索できる強さを、一緒に育てていければと思います。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
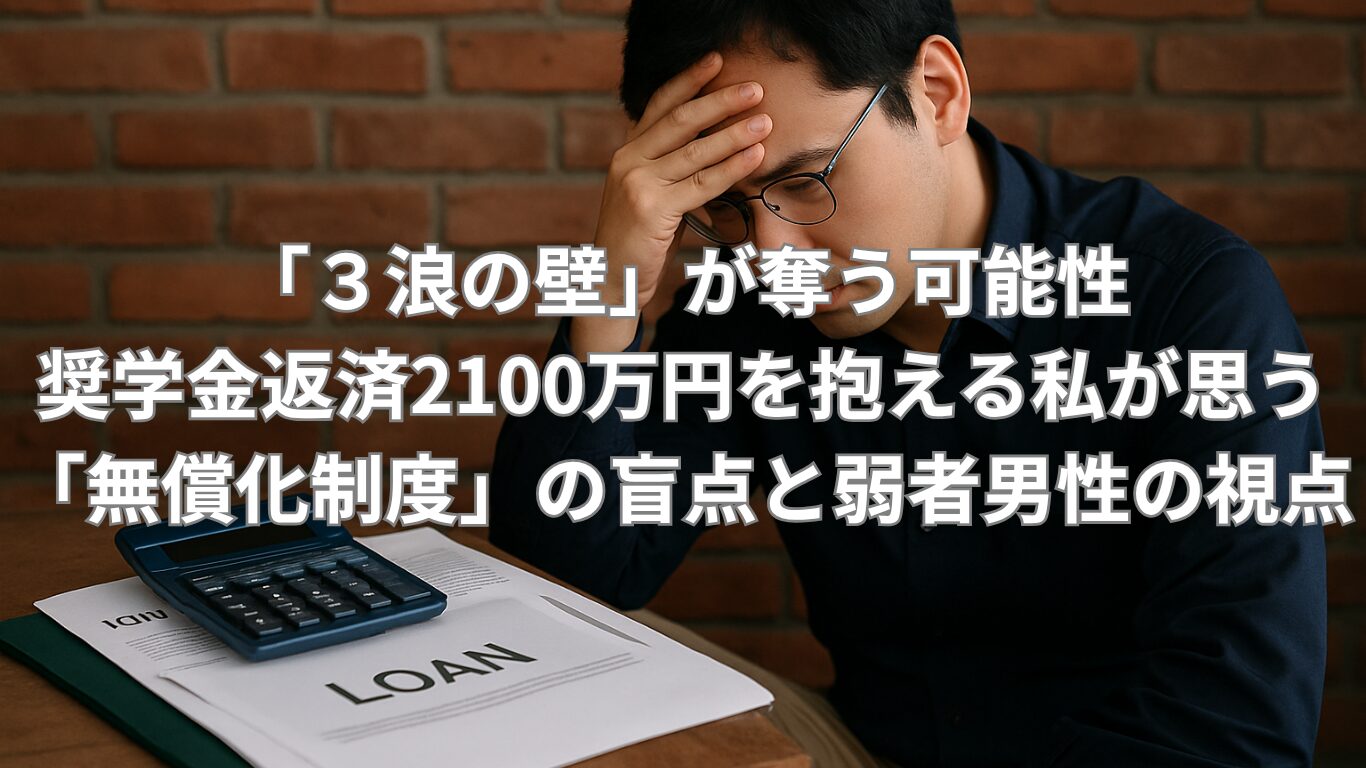
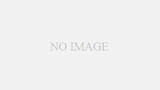

コメント