こんにちは、奨学金男です。
私は、父を高校2年で亡くし、母子家庭で3浪の末に6年制の私立大学へ進学し、国家資格を得て働いています。身長168cm、独身。
総額2100万円以上の借金(奨学金・教育ローン)を背負って社会に出ました。
毎月の返済に追われる生活の中で、「働くとは何か」を自分なりに考える日々を過ごしています。
今日は少し過激に聞こえるかもしれませんが、
「サラリーマン根性から抜けるには、無職になるのが一番いいのかもしれない」
というテーマで書きます。
きっかけは、X(旧Twitter)で見たあるポストでした。
投稿主の大塚あみさんが、こんなことを書いていたんです。
最初は笑ってスクロールしようと思いました。
でも、指が止まった。
「無職って、もしかしたら“リセット”の形なんじゃないか?」
そう思ってしまったからです。
サラリーマン根性は、麻酔のようなものだ
私には“サラリーマン根性”が深く染みついています。
「言われたことを、言われたようにやる」
「怒られない範囲で動く」
「毎月の給料日まで何とかやり過ごす」
この思考で、バイト時代を含めて10年以上生きてきました。
正直、この根性は社会では優秀な適応装置です。
組織のルールを守り、ミスを減らし、同僚と摩擦を起こさずやり過ごす。
それだけで生活は続くし、周囲からも「真面目な人」と言われます。
でも、その“真面目さ”が、いつの間にか自分の首を締めていました。
奨学金の返済は待ってくれません。
「今日も定額が振り込まれる」という安心感の裏で、
“未来の負債”が確実に増えていく。
安全に見える道が、実は一番危険だった――そう気づきました。
サラリーマン根性とは、言い換えれば「思考停止の快適さ」。
考えなくても生活は続き、動かなくても給料は出る。
それが続くうちに、「自分で決める筋肉」が衰えていくのだと思います。
無職の人たちは、“自分で決める筋肉”を鍛えている
無職と聞くと、多くの人が「怠け者」や「社会不適合」を連想するでしょう。
でも、あの投稿をきっかけに、私は逆の見方をしてみました。
「無職になる」とは、“自分の意思で一度システムを降りる”こと。
会社員を辞めた瞬間、周囲からすべての指示が消える。
何時に起きてもいい。どこに行ってもいい。何をしても怒られない。
それは一見、天国のようで、同時に地獄の始まりでもあります。
誰もあなたを守ってくれない。
時間の使い方、食費のやりくり、食い扶持をどうするか――
すべて自分で“設計”しなければならない。
でも、そこで初めて気づくんだと思います。
「今まで、自分で何も決めていなかった」と。
無職になると、「意味のない仕事」の正体が見える
私は給料明細を見るたびに思っていました。
「これだけ働いて、手取りこれだけ?」と。
残業もこなし、休日出勤もして、数字上は“頑張っている”。
でも、ふと冷静になると――
自分が何のために働いているのか、わからなくなっていました。
「会社の売上を伸ばすため」でもなければ、
「社会を良くするため」でもない。
ただ、「来月も給料をもらうため」に働いているだけ。
その構造こそ、サラリーマン根性の温床です。
“意味”を感じない労働に時間を使い続けるうちに、
「働く=我慢」だと信じ込んでしまう。
けれど、無職になると、その構造が一気に剝がれます。
働かなくても朝は来る。
給料日は来ないけれど、月は回る。
「生きるための仕事」と「意味のない仕事」の境界線が、くっきり見えてくるのだと思います。
「ハローワークからお金がもらえる」という現実も、見逃せない
大塚さんの投稿の中で、特に印象に残ったのがこの一文です。
「しかも、退職すればハロワからお金が貰えてお得!」
皮肉にも思えますが、確かにその側面はあります。
雇用保険に加入していれば、失業給付金を受け取る権利がある。
つまり、「働かなくても、一定期間は生きていける制度」があるということ。
日本では、失業は“恥”のように語られがちですが、
制度としては、ちゃんと“休む権利”が用意されています。
「働かない=怠け」ではなく、
「働かない期間=思考のリハビリ期間」と捉えた方が健全だと、私は思います。
今の私は、
「この仕事を一生続ける自信がない」
「毎日が苦しいけど、辞めるのも怖い」
と感じています。
“無職になる”という選択肢が、頭の中をよぎっています。
無職は、究極の「設計変更」である
会社員という制度の中では、すべてがあらかじめ決められている。
起きる時間、働く場所、評価の基準。
その枠組みの中で「もっと自由に生きたい」と叫んでも、
土台が変わらなければ、何も変わらない。
だからこそ、一度、土台ごと壊す。
これが無職になる最大の意味かもしれません。
“働くとは何か”を考える前に、
“働かなくても何が残るか”を見てみる。
残ったものが、私の本質かもしれない。
誰かの承認でも、会社の評価でもなく、
自分が「これをしていると生きている」と感じるもの。
それを見つけるには、
サラリーマン根性に覆われた日常から、一度抜け出すしかない――今はそう思っています。
無職になる勇気が、「働き方を変える勇気」につながる
多くの人は「辞める勇気」がない。少なくとも私はそうです。
でも、本当に必要なのは「無職になる勇気」そのものではなく、
“自分の生活を再設計する勇気”かもしれません。
無職は、社会的な肩書きを一度失う行為。
同時に、自分の肩書きを自分で作り直すチャンスでもあります。
SNSで情報を発信するのもいい。
ハンドメイドを売ってみるのもいい。
地域のボランティアに参加してみるのもいい。
“誰かに雇われない時間”の中で、
「自分の得意」を社会と接続する方法を探る。
それが、次の働き方を決めるコンパスになる。
「貧困から抜け出す」とは、“自分で稼ぐ感覚”を取り戻すこと
私は奨学金2100万円を返済しながら生きています。
返済額を見るたびに、気が遠くなります。
でも、だからこそ、
「自分の力でお金を生む感覚」を持つことが、唯一の希望です。
サラリーマン根性は、この感覚を麻痺させる。
「働いた分、給料がもらえる」は、
実は“自分で稼いでいる”ようでいて、“会社が分配してくれている”だけ。
無職になることで、その構造は明確になります。
働かなければ=収入ゼロ。
働けば=少しでも入ってくる。
たとえ500円でも、自分で稼いだお金は、
サラリーマン時代の5万円より重い。
この重みを思い出すために、
一度、無職という「空白」を経験するのは、決して悪くない――そう思ってしまう。
ただし、私は毎月の返済がある。リスクは大きい。その現実は見失わないようにしたい。
まとめ:「無職はリセットではなく、リデザインだ」
私はいま、サラリーマン根性から抜け出したいと強く思っています。
思うだけでは、根本的な変化は起きません。
それでも、こう考えています。
「無職になること」は、最も強力で最速の“再設計ボタン”だと。
もちろん、現実にはすぐ辞められない人も多い。
奨学金の返済、家賃、生活費。私もそのひとりです。
それでも、「無職になる選択肢がある」と思うだけで、
今の仕事との距離が少し変わる。
“仕方なく働く”ではなく、“自分で選んで働く”に近づく。
それが、サラリーマン根性から抜ける第一歩だと思います。
働かない勇気。
それは、逃げではなく再設計のための一時停止。
そして、そこから生まれる「自分で決める力」こそ、
奨学金返済に追われる私たちが本当に必要としているものだと思います。
ここに書いたことは、私自身への戒めであり、これからの実験ログです。
同じように「働くこと」に息苦しさを感じている誰かの、
小さな勇気の種になれば嬉しいです。
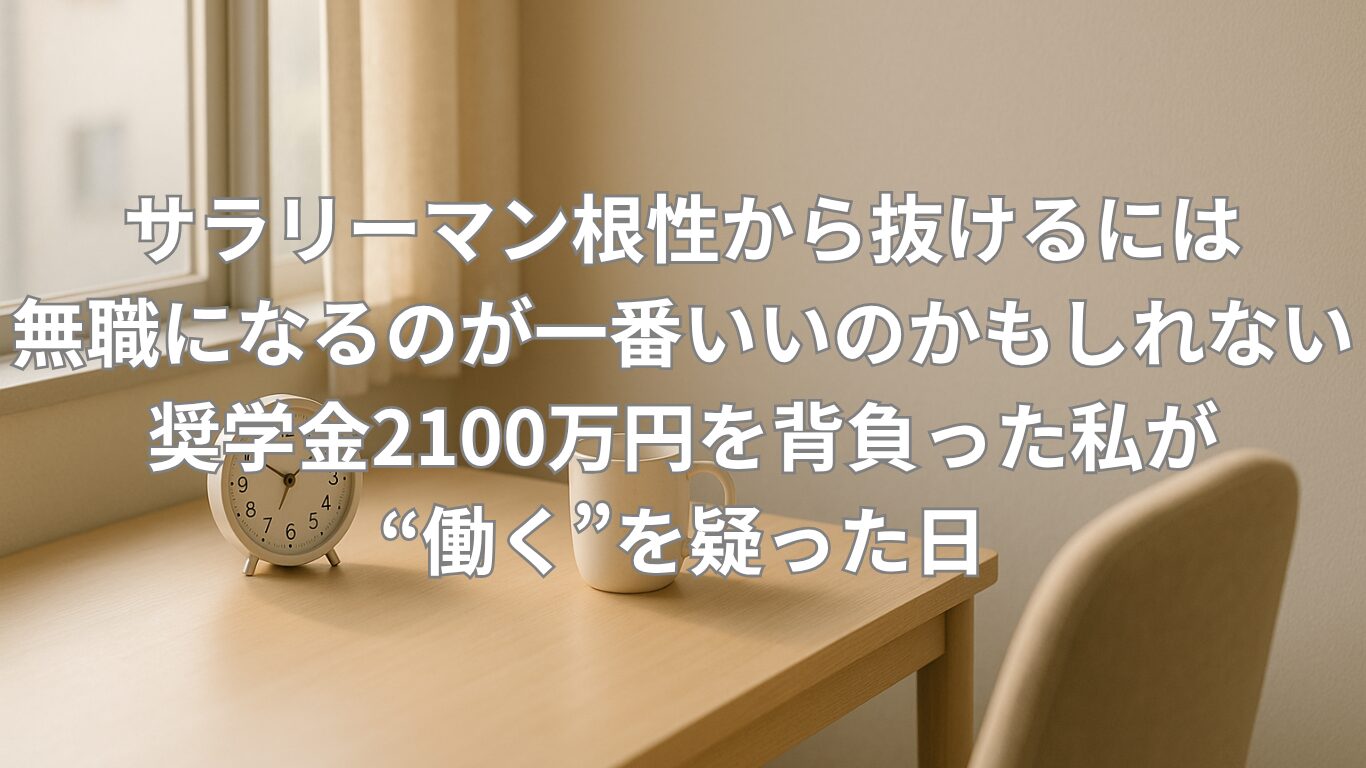
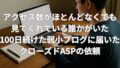
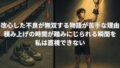
コメント