こんにちは、奨学金男です。
私は、高校2年の時に父を亡くしました。母子家庭で3浪の末、6年制の私立大学に進み、国家資格を取って働いています。身長168cm、独身。社会に出る時点で背負っていた借金(奨学金+教育ローン)は総額2100万円以上。毎月の返済に追われながらも、「脱・弱者男性」「貧困から抜け出す」「奨学金返済のリアル」をテーマに、ここで日々のことや考えていることを書いています。
今日は、ひとつ実験の報告です。
このブログの一番はじめに書いた「自己紹介の記事」を、少しだけ修正してnoteにも載せてみました。結果はシンプルです。1日のインプレッション数は10倍に増えた。けれど、コメントはゼロ。ブログと同じく、静かなままでした。
どうして実験したのか――「届いていない」焦り
「書いても読まれない」。この現実を、私は何度も味わってきました。
仕事を終えて帰宅し、眠い目をこすって文章を整える。公開ボタンを押して、数時間ごとにアクセスを見る。でも数字は伸びない。自分の人生を切り出して、弱さも未熟さも正直に書いても、画面の向こうは無反応。これはなかなか堪えます。
そんな時に目に入ったのが、「noteに出すと最初の露出が得やすい」という話でした。アルゴリズムの仕組み、プラットフォームの文化、タグの効き方。たしかに、ブログは“陸の孤島”になりがちです。検索で見つけてもらえるようになるまで時間がかかるし、SNSに流しても反応は安定しない。だったら、一度土俵を変えてみよう――そう考えたのが実験の理由です。
結果――インプレッション10倍、でも静かなまま
数字の変化だけ言えば、noteの勝ちです。
プラットフォームの特性上、公開直後から“見られる場所”に置かれやすい。タイムライン、タグ、フォローのネットワーク、編集部のピックアップ――こうした要素が最初の露出の壁を低くしているのだと思います。私の自己紹介記事も、1日のインプレッションはここ(ブログ)の約10倍になりました。
でも、コメントはゼロ。
ブログと同じでした。静かなまま、何も起きない。数値上は「見られた」のに、「読まれ」「届き」「交わる」には至らなかった。嬉しさと虚しさが同居する、不思議な感覚でした。
なぜ“見られた”のに“届かなかった”のか――3つの仮説
1) 自己紹介は「通過点」であって、会話のきっかけになりにくい
自己紹介は、出会いのドアノブみたいなもの。回して中に入れば会話が始まるけれど、ドアの前で立ち止まる理由は薄い。「あなたは誰か」はわかっても、「私(読者)は何を話せるのか」が示されていない。読者視点の“参加口”がないのだと思います。
2) 物語は「共感」で止まりやすく、コメントには「利得」か「問い」が必要
私のプロフィールは、ある種のドラマ性があります。父の死、母子家庭、3浪、6年制私立、国家資格、借金2100万円。読めば“重さ”は伝わる。でも、重さは共感を呼んでも、コメントを押す動機にはなりにくい。コメントが生まれるのは、「答えたい問い」や「語ることで得られる何か(情報の交換、仲間の合図、自己の整理)」があるときです。
3) 行動の指示が弱い(CTA不在)
noteにもブログにも、「あなたはどう思いますか?」「同じ状況の方は、ここに書いてください」という明確な呼びかけをほとんど置いていませんでした。読者は善意で動くときもあるけれど、たいていは“言われたら動く”。その一言が抜けていた。
noteで露出が増える理由――仕組みの観察メモ
- タイムライン型の新着導線:公開直後の数時間に“流れ”へ自然露出。
- タグのハブ化:「奨学金」「貧困」「就職」「弱者男性」などのタグで周回導線ができる。
- フォロー・スキの波及:少数でもフォロー・スキが付けば、そのネットワークに二次露出。
- プラットフォームの“読む準備”:noteは「読むために来る場所」。検索で偶然流入するブログと違い、受け手のモードが“読書寄り”になっている。
この仕組みが“最初の見られ”を後押しして、インプレッション10倍という結果につながったのだと思います。
それでもコメントが付かない理由――読者の“コスト”を考える
読むことと、書くこと(コメントすること)の間には大きな段差があります。
読むのは数分の投資。書くのは、感情の言語化と時間の投資。さらに、弱さやお金の話は匿名でも書きにくい。奨学金や貧困は、いまも多くの人にとって「心の内側の話」で、公共の場に置くには勇気がいる。だから、無反応は必ずしも無関心ではない――これは、私自身が“書けなかった側”だったときの感覚からも、よくわかります。
自己紹介の再設計――“読む”から“交わる”へ
今回の学びをもとに、自己紹介を会話の入口に作り替えます。
- 読者の状況を直接呼びかける
「奨学金の返済額が月◯円以上の方へ」「返済を家族に言えず抱えている方へ」――誰の物語なのかを、冒頭で“読者の言葉”に置き換える。 - 質問を埋め込む
「あなたの返済の一番の悩みは何ですか?」
「家賃・食費・奨学金、どれを最初に削っていますか?」
読者が答えやすい小さな問いを2〜3個。 - 体験の“使い道”を示す
例:「私の返済スケジュール表(匿名・金額改変版)を配布します」
例:「就職1年目〜3年目の返済ミスと、その修正手順を記事末にまとめました」
読む→役に立つへ橋を架ける。 - 感情の“安全基地”を置く
「弱音を吐いてもOK」「匿名でのひとこと歓迎」――センシティブな話題だからこそ、安心して“書ける”と伝える。
私のプロフィールは、“あなた”の物語につながるのか
私は、借金2100万円以上の現実を抱えて働いています。
生まれや家計は選べないし、突然の不幸は待ってくれない。努力は報われることもあるけれど、努力ではねじ伏せられない“差”も確かにある。このブログは、そうした差の中であがく私の記録です。同時に、同じ場所で立ち尽くしている誰かの足元に、小さな足場を置くための場所でもあります。
私は「強くなれ」とは言いません。
ただ、「弱さを持ったままでも前に進める道」を一緒に探したい。
返済が生活を飲み込む夜、コンビニのコーヒーを我慢した朝、電卓を叩いて絶望した給料日。そういう具体の時間を、生活の言葉で共有していきます。
インプレッション10倍の解釈――数は“合図”、対話は“設計”
露出が増えること自体は、やっぱり救いでした。
誰かのタイムラインに、数秒でも私の生が触れた――その事実は、孤独をほんの少しだけ薄めてくれる。けれど、数は合図にすぎない。対話は設計しないと生まれない。今回の実験で、それがはっきりしました。
- 数=合図:届く可能性がある、というサイン。
- 対話=設計:問い、呼びかけ、居場所のルール、役に立つ具体物。
この2つを分けて考えることが、これからの書き方を変えていくと思います。
次の一手――同じ内容を「読者起点」に書き換える
- 自己紹介の二層化
- 上層:30秒で読める“あなた向け”の要約(問いと導線付き)。
- 下層:背景の物語(父の死、3浪、6年制私立、国家資格、2100万円)。
- 「返済の現実」を数値で見える化
毎月の返済額、金利、生活費の内訳を“モデル世帯”にして提示。
読者が自分の数字を当てはめやすいフォーマットにする。 - 会話を生む小さな土台
「あなたの返済ストーリーを1行で」など、短文で返せる問いを記事末に。
匿名で書けるフォームや、簡単なアンケートを用意する。 - 投稿時間と初速の最適化
平日夜・休日午前など、読まれやすい時間に公開して“最初の波”を取りに行く。
その波の中に、問いと導線を置く。
それでも無反応だったら――それは敗北ではなく、準備運動
無反応は、たしかに心を削ります。
でも、今はこう捉えます。「あなたに届く準備が、まだ整っていないだけ」。書き方、見せ方、問いの置き方、安心の作り方。やることは山ほどある。私の暮らしは相変わらずカツカツで、返済は待ってくれない。それでも、文字にして並べると、どうにか一歩踏み出せる気がします。
読んでくれたあなたへ
ここまで読んでくれて、ありがとうございます。
もし、あなたも奨学金の返済で眠れない夜があるなら、「いま一番苦しいポイント」を、心の中だけでも言葉にしてみてください。家賃? 食費? 人間関係? 働き方? 数字にすると、戦う順番が見えてきます。私はこれからも、生活の言葉で、生活の現実を書いていきます。
今回の実験は、インプレッション10倍/コメント0という結果でした。
でも、これで終わりにはしません。“見られる”を“交わる”へ。その橋のかけ方を、これからの更新で試していきます。あなたの足元にも、私の足元にも、同じ強度の足場が必要です。焦らずに、でも止まらずに、置いていきます。
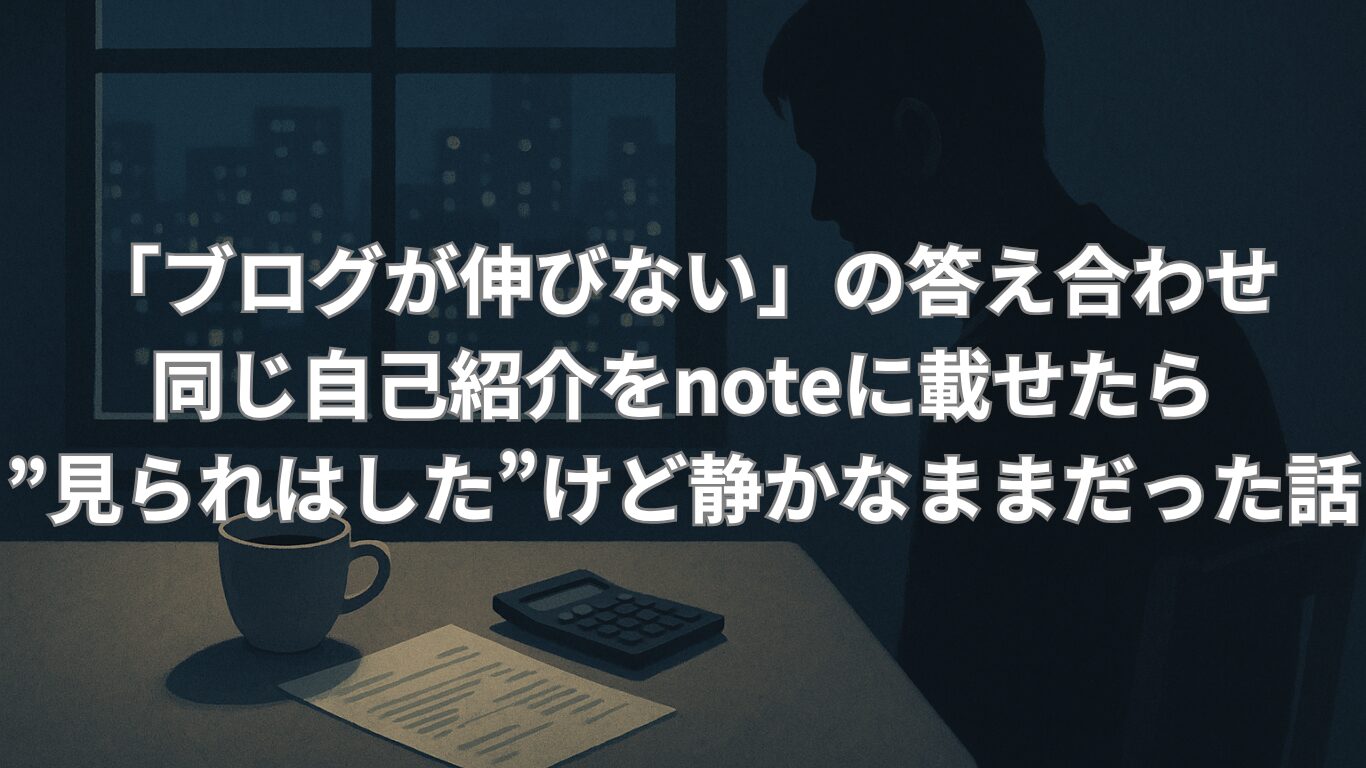
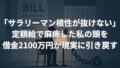

コメント