こんにちは、奨学金男です。
少し前に、「早起き習慣が身についた」と嬉しそうに書いた記事を公開しました。
アメリカ出張から帰って、朝5時に自然と目が覚めるようになり、コーヒーを飲みながら静かな朝を過ごす──そんな“人生のリズム”がやっと掴めたような気がしていました。
けれど、あれから数日。
気がつけば、生活は完全に“元通り”になっていました。
朝はギリギリまで寝て、遅刻しそうになって飛び起きる。
夜はスマホを見ながらダラダラ起きて、気づけば日付が変わっている。
休日は昼まで寝て、「また無駄に過ごした」と自己嫌悪に沈む。
結局、私は“いつもの私”に戻ってしまったのです。
「続かない自分」を責める朝
最初のうちは、「ちょっと疲れてるだけだ」と思っていました。
出張疲れ、仕事のストレス、気温の変化。
どれも理由になりそうな気がして、言い訳にしていました。
日が経つうちに、明らかに自分の生活リズムが崩れていくのがわかりました。
朝5時に起きていたのが、6時、7時、そして8時。
気づけば、出勤時間ギリギリに起きる毎日に戻っていました。
「やっぱり自分は続かないんだな」
そう呟いた瞬間、胸の奥がずしんと重くなりました。
早起きが続かなかったことよりも、「また失敗した」という感覚がつらかった。
自己管理もできない弱い自分。
何度も立て直そうとして、結局元に戻る。
まるで、奨学金の返済みたいだと思いました。
毎月返しても、残高はなかなか減らない。
努力しても、実感がない。
“終わりの見えない戦い”という点で、どこか似ているんです。
「生活習慣」は才能じゃない。けれど、環境に左右される
私は昔から生活リズムが安定しません。
高校時代は、夜遅くまでテレビを見て、朝早くから朝練に行き、授業は爆睡。
浪人時代は、夜遅くまでテレビを見て、朝はギリギリまで寝ている。
大学時代は、深夜バイトをしたり、一夜漬けで試験を迎えたり、午前の授業はさぼったり。
そのまま社会人になったので、「夜型」が体に染みついているのです。
でも、これは単なる“怠け”ではないと思っています。
貧困家庭に生まれ、バイトや勉強を詰め込まないと生きていけなかった。
だから、“余裕のある生活リズム”というものを、最初から知らないんです。
裕福な人たちは、早起きが「健康習慣」や「自己投資」として語られます。
けれど、貧困層にとっての早起きは、“戦いの始まり”です。
朝早く起きること自体が、もうすでに疲れる。
寝不足のまま仕事に行き、残業して、帰ってくるころにはもう翌日の気力が残っていない。
生活習慣を整えるというのは、実は「お金と時間に余裕がある人」にしかできない贅沢なのかもしれません。
「朝の静けさ」を失って見えた現実
朝5時に起きていた頃、私は自分が少しだけ“まともな人間”になれた気がしていました。
太陽の光、温かいコーヒー、静かな時間。
それだけで、少しだけ幸福を感じられた。
けれど今は、朝の静けさを感じる余裕すらない。
アラームを何度も止めて、飛び起きて、慌てて支度して出勤。
電車の中で「昨日も何もできなかった」とスマホを見ながら落ち込む。
そうやって一日を始めると、すべてが後手に回ります。
遅れ、焦り、疲労、自己嫌悪。
まるで「負のスパイラル」が再生産されているようです。
貧困というのは、単にお金がないだけではなく、「心のリズムを奪うもの」だと思います。
時間を支配される。
休むことに罪悪感を覚える。
そして、いつの間にか「普通に暮らす力」そのものが失われていく。
だから、早起きできなくなった自分を責めるのは、もうやめました。
私が弱いのではなく、社会の構造が厳しすぎるんです。
「努力が報われない」ときに感じる孤独
早起きが続かなかったことは、ほんの小さな挫折です。
でも、その裏には“報われなさ”が潜んでいます。
どれだけ頑張っても、貯金は増えない。
どれだけ節約しても、奨学金の返済は減らない。
努力しても、周りは変わらない。
そんな現実の中で、「生活習慣を変える」なんて気力が持つはずもない。
SNSでは、「朝活」「モーニングルーティン」「成功者の習慣」なんて言葉が溢れています。
でも、彼らが見せる“理想の生活”は、私たちの現実とはまるで別世界。
朝日を浴びながらランニングできる余裕がある人は、そもそも“弱者”ではないんです。
私たちは、「明日どう生き延びるか」で精一杯なんです。
それでも「また早起きしたい」と思う理由
それでも、私は諦めていません。
早起きできなくなっても、また挑戦したいと思っています。
なぜなら、“あの朝の静けさ”を一度でも経験した人ならわかると思うんです。
あの時間だけは、貧困も、奨学金も、社会の格差も関係なくなれる。
お金がなくても、心が少し自由になれる。
私は今も、毎朝アラームを5回くらい止めてしまいます。
それでも、週に1回でも、気分が乗った日だけでもいい。
朝に少しだけ早く起きて、窓を開けて空気を入れ替える。
それだけでも、心の中に“希望の種”が残る気がします。
早起きは習慣にならなかったけれど、“希望の記憶”としては確かに残りました。
「続けられない」ことを受け入れる勇気
人はよく、「継続こそ力なり」と言います。
確かにそれは正しい。
けれど、弱者として生きてきた私には、「継続」よりも「再開」のほうが大切に思える。
何度やめても、何度戻っても、またやり直せる。
続けられなくても、失敗じゃない。
再び立ち上がる力こそ、弱者が生き残るための武器です。
私は、3浪して大学に入り、6年制の学費を背負って国家資格を取った。
その道のりも、途中で何度も挫折しました。
それでも、少しずつ前に進んできた。
生活習慣も、きっと同じだと思う。
一度崩れても、また整えればいい。
その繰り返しの中にしか、“現実を生きる力”は育たないのだと信じています。
さいごに:「完璧じゃない生き方」を肯定したい
私はまた、夜寝付けません。
この記事を書きながら、眠いと思っていますが、ベッドに入っても寝付けないと思います。
画面を見つめながらため息をつく。
明日もきっと、朝はギリギリに起きるでしょう。
でも、そんな自分を嫌いにならないようにしたい。
完璧に生きることはできなくても、立ち止まって考えられるなら、それでいい。
弱者男性として、貧困の中で生きてきた私がいま大事にしたいのは、“諦めない姿勢”です。
たとえ早起き習慣が3日で終わっても、
たとえ生活リズムが乱れても、
また挑戦しようと思えるなら、それはまだ希望があるということ。
そして、朝の光はいつだって同じ場所にある。
私がまた立ち上がる日を、静かに待っていてくれる。
「続かない自分」でもいい。
それでも、生きようとする自分を、少しだけ誇りたい。
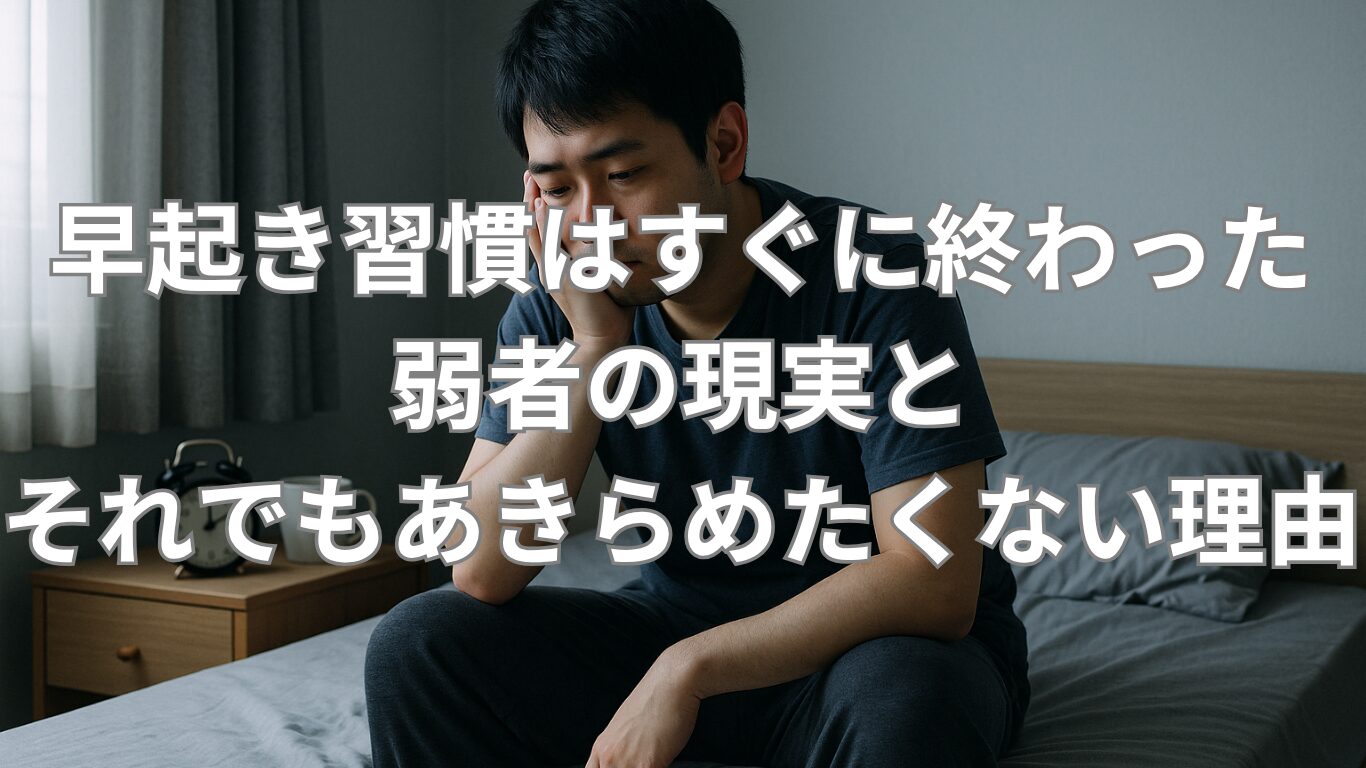
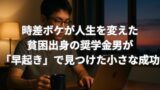
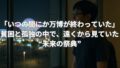

コメント