こんにちは、奨学金男です。
ここ最近、どこのニュースを開いても「総裁選」「新しい首相」「内閣人事」──そんな政治の話題で持ちきりです。
SNSでも、「政治が面白くなってきた」「誰がどんな政策を出すのか楽しみ」といった声を見かけます。
けれど、正直なところ、私は政治を「面白い」と感じたことがありません。
むしろ、「もう誰でもいいから、生活を少しでもマシにしてくれ」と思っています。
私のように、貧困と奨学金返済に追われている人間にとって、政治は「娯楽」ではなく「生存条件」に近いものです。
だからこそ、「政治って面白いよね」と言える人を、どこか羨ましく、そして少し妬ましく感じてしまうのです。
政治が「遠い話」に感じる理由
私が政治に興味を持てなかったのは、たぶん家庭環境も大きいと思います。
高校2年のときに父を亡くし、母子家庭で育ちました。
母は朝から晩まで働き詰めで、政治の話なんてしたこともなかった。
選挙の日、母が選挙に行っていたかどうかも知りません。
そんな環境で育った私は、「政治=関係のないもの」と思い込んでいました。
政治はテレビの中の人たちがするゲームみたいなもので、私のような一介の庶民には関係のない世界。
でも、大学に入り、奨学金を借り、社会に出て──ようやく気づいたのです。
「いや、政治ってめちゃくちゃ生活に関係あるじゃん」と。
2100万円の奨学金と「自己責任」という言葉
私は6年制の私立大学に通いました。国家資格を取るために必要な選択でしたが、その結果、奨学金の総額は2100万円を超えました。
返済は20年。毎月の支払いをこなすだけで精一杯です。
そんな生活の中で、「政治の話題が盛り上がっている」なんてニュースを見ると、正直、心のどこかが冷めてしまうのです。
──だって、政治がどんなに“面白く”ても、私の生活はちっとも楽にならないから。
「自己責任」という言葉が流行った頃から、弱者はいつも切り捨てられてきました。
教育費も、医療費も、住宅費も高いまま。
奨学金は“借金”であり、「頑張って返せ」という前提が変わらない。
国が若者の未来を支えるというより、「借りたなら返せ」「無理なら諦めろ」と言っているように聞こえます。
それが“政治の現実”なのだとしたら、私はどうしてそれを「面白い」と思えるでしょうか。
SNSの「政治が面白い」発言に感じる違和感
最近、SNSで「政治を学ぶのが楽しい」「政策を分析するのが面白い」という投稿を見ました。
それ自体は素晴らしいことだと思います。社会に関心を持つのは大事です。
でも、ふと考えるのです。
「その人たちは、生活がかかっていないから“面白い”と言えるんじゃないか?」と。
私は、家賃と奨学金と光熱費で月の大半が消えるような暮らしをしています。
政治がどう動こうが、今月の支払いは待ってくれない。
誰が総裁になっても、ガソリン代も、食料品も、電気代も上がり続けている。
「政治が面白い」と言えるほどの心の余裕なんて、どこにもないのです。
政治を楽しめる人たちは、ある意味“勝ち組”なのだと思います。
彼らに悪意はないでしょう。
でも、その距離感に、どうしても寂しさを感じてしまうのです。
「政治が面白い」と言えない自分を責めていた時期
実は一時期、「政治に興味を持てない自分はダメなんじゃないか」と思っていたことがあります。
社会人として、もっと世の中の動きを知るべきだ。
投票だけでなく、政策にも詳しくなるべきだ。
──そう頭では分かっているのに、心がついてこない。
なぜなら、政治を知れば知るほど、「結局、弱者は報われない」という現実を突きつけられるからです。
例えば、教育無償化の話。
確かに良いことですが、対象は限定的だったり、条件が厳しかったりする。
私のように既に奨学金で人生を背負った人間には、救いがない。
「知っても変わらない」
「わかっても苦しくなるだけ」
そんな気持ちが、政治への関心を遠ざけていったのだと思います。
政治は「希望」ではなく「現実」
世の中の多くの人が、政治に「希望」や「変化」を求めていると思います。
でも、私にとって政治は「希望」ではなく、「現実」そのものです。
税金、物価、奨学金制度、医療費──
すべて政治によって決まる。
それはまるで、見えない巨大な歯車に押しつぶされながら生きているような感覚です。
どんなに努力しても、政治の流れ一つで生活が悪化する。
「自己責任」で済ませられる範囲を超えているのに、助けは届かない。
政治は、面白いかどうかではなく、生きるか死ぬかの問題なのです。
「政治が面白い」と言える日が来るとしたら
それでも、私は政治を完全に諦めているわけではありません。
もし将来、私が「政治が面白い」と思える日が来るとしたら──それは、生活が少しでも安定してからだと思います。
奨学金を完済して、家賃を気にせずに暮らせて、
将来の不安よりも今日の晩ご飯の方を気軽に考えられるようになったとき。
そのとき初めて、「ああ、政治って面白いな」と言えるのかもしれません。
つまり、「政治が面白い」と感じられるかどうかは、
その人の生活の余裕と直結している。
だから私は、今の自分を責めるのをやめました。
政治に興味を持てないのは、無関心ではなく、「生きるのに精一杯だから」なんです。
それでも投票には行く
「政治が面白くない」と言いながら、私は選挙には行きます。
なぜなら、誰がトップになっても、ほんの少しでも自分の生活が楽になる可能性を信じたいからです。
政治に期待しすぎるのは危険かもしれません。
でも、完全に諦めたら、それこそ終わりだと思うのです。
投票という行動は、私にとって“希望”ではなく“抵抗”です。
「この国に、少しでも弱者の声を届かせたい」──それが、せめてもの意思表示。
おわりに:政治は「面白くなくていい」
最近では、政治系のYouTuberやインフルエンサーが増えています。
彼らの語りは確かに勉強になりますが、同時に「この人たちには余裕がある」と感じる瞬間もあります。
でも、それでいいのかもしれません。
政治を「面白い」と言える人がいれば、私のように「面白くない」と感じる人もいていい。
どちらも、この国の現実を映しているのです。
私は今日も、2100万円の奨学金を返しながら、
「誰でもいいから、少しでもこの国をマシにしてくれ」と願っています。
政治が面白いかどうかよりも、
生きることが少しでも楽になる社会を、私は望んでいます。
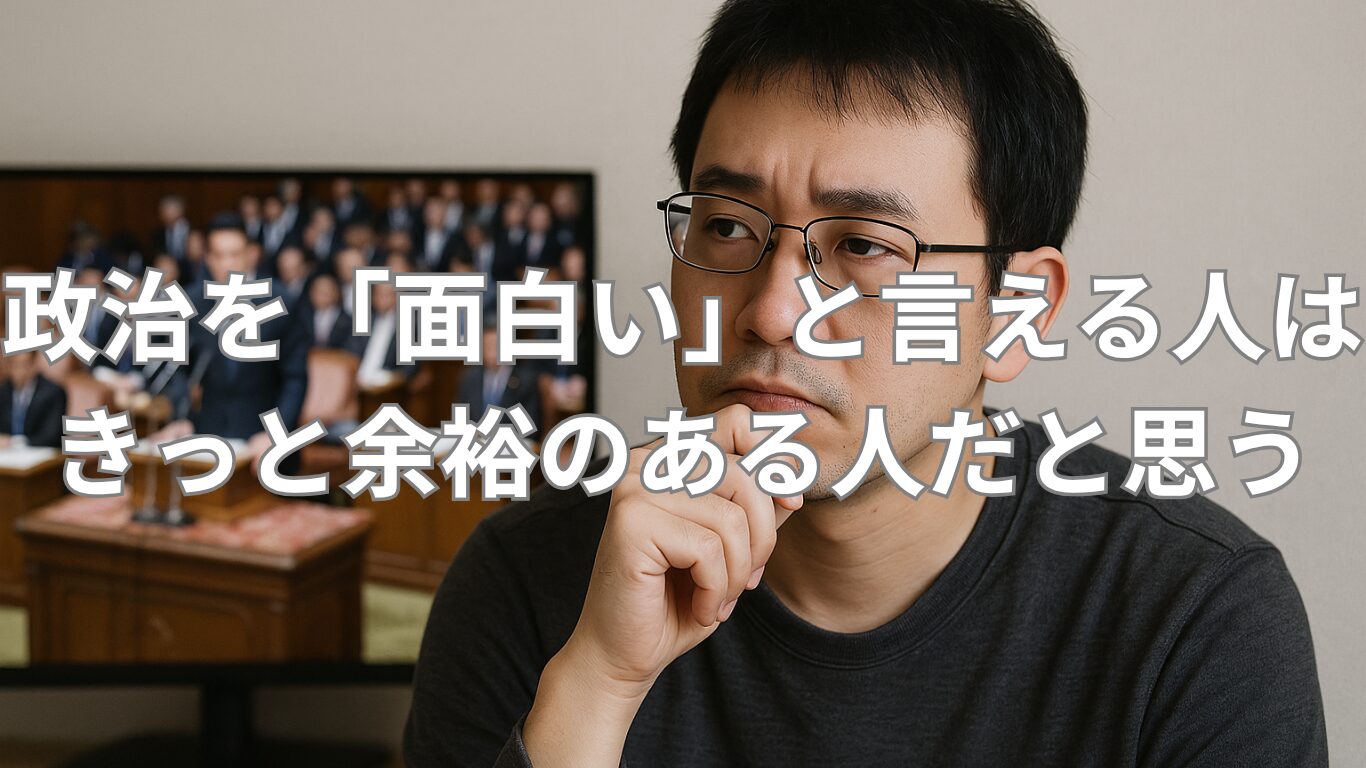
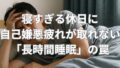
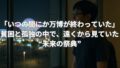
コメント