こんにちは、奨学金男です。
私は現在、月々奨学金を返済しながらNISAで少しずつ積み立て投資をしています。奨学金の総額は2100万円以上。高校2年で父を亡くし、母子家庭で3浪して、6年制の私立大学を卒業。国家資格を取得し、なんとか正社員として働いています。
身長は168cm、独身です。
このブログでは、「脱弱者男性」×「貧困」×「奨学金返済」という現代日本のリアルに切り込んでいます。今回は、「墓じまい」が過去最多になっている時代に、なぜ私は亡き父の墓を“建てた”のかについてお話ししたいと思います。
私についてはこちらの記事を読んでください。
墓じまい急増の背景
最近、ニュースやネットでも「墓じまい」という言葉をよく見かけます。
実際、墓じまい(お墓を撤去し更地に戻して墓地使用権を返すこと)は、年々増加しており、2013年度に約88,000件だったのが、2023年度には約167,000件とほぼ倍増。過去最多を記録しています。
墓じまいが増える背景には、次のような要因があります。
- 少子高齢化・核家族化
→ 子どもが遠方に住んでいて管理できない - 経済的理由
→ お布施や管理費など、維持コストの負担が大きい - 価値観の変化
→「子どもに負担をかけたくない」「お寺付き合いが面倒」など
こうした流れから、今は樹木葬・納骨堂・手元供養・ゼロ葬といった新しい供養方法が広まり、「墓を持たない選択」が増えています。
墓を建てるなんて、時代錯誤?
そんな時代に、私はあえて「墓を建てる」選択をしました。
正直、かなり迷いました。墓代って、安くないんです。国産の石を使うとなると、墓石・永代使用料・建立費などで総額250万円近く。実はこのお金、本来であれば父の死亡時に用意されていたものだったのですが、私はそれを高校生活と浪人生活に食いつぶしてしまったのです。
高校卒業のためと大学へ行くための浪人時、奨学金と教育ローンを借りて、母のパート代も合わせて、なんとか私立の6年制大学に進学。結果として、父のために使われるべき墓代は消えました。
そして社会人になり、毎月奨学金を返しながら、NISAを始めて、少しずつ貯金をして――。
ようやく、数年がかりで「母の願いだった、父の墓を建てること」を実現できたのです。
墓を建てた理由①:「母の想い」
私が墓を建てた最大の理由は、「母の顔」です。
母は父を突然失ってからずっと、生活のために働き詰めでした。年金も少なく、再婚もしないで、私を大学まで行かせてくれました。
そんな激動とも言える毎日を過ごしながらも母が1日たりとも仏壇に手を合わせなかった日はありません。
本当に父を愛していたということが分かります。
そして、父のために墓を建てたいという言葉は言ってきませんでしたが、想いはひしひしと伝わってきました。
そして、母が亡くなった後も最愛の父と同じ墓で一緒に過ごしてほしいと思いました。
墓を建てた理由②:「自分のルーツへの責任感」
貧困家庭に生まれ、浪人生活を送り、今も奨学金返済を抱える私にとって、「父の墓を建てる」という行為は、ある意味“逆行”だったかもしれません。
でも、「貧乏な家庭に生まれたからといって、先祖や親を粗末にしていいのか?」と自問自答することも多かったんです。
誰にも継がれず撤去される無縁墓が増えるこの時代に、「せめて父の遺骨は、きちんとした場所に眠らせてやりたい」。そして、「母が安心して逝けるように、父とまた一緒にいられると思ってもらいたい」そんな思いをずっと持っていました。
墓を建てた理由③:「弱者男性でも“何かを返せる”という実感」
私は「弱者男性」という言葉に敏感です。非モテ、低身長、非正規、貧困……この社会で“勝ち組”とは程遠い自分。でも、だからこそ、「自分の中にある誇り」は大切にしたい。
世間から見れば、小さなことかもしれません。
でも、「父の墓を建てた」という事実は、私にとってひとつの“誇り”であり、“達成感”でした。
そしてそれは、ただの自己満足ではなく、「自分の原点に感謝を返す」という、人として当たり前の行為だったと今は思えます。
それでも奨学金返済は続く
もちろん、墓を建てたからといって生活が楽になったわけではありません。
奨学金はいっぱい残っています。繰り上げ返済はしていないので10年以上返済期間があります。
将来、もし自分が結婚して子どもを持つことがあったとしても――。
「親の借金」と「親の墓」のどちらを残したいか。
私は、「親の借金は残さないけど、親の墓は残したい」と思っています。
墓を建ててよかった?――正直な気持ち
結論から言うと、「建ててよかった」です。
- 母が嬉しそうに線香をあげていた姿
- 父の名が刻まれた墓石を見て、涙が出そうになった瞬間
- 貧困でボロボロだった過去の自分を、少しだけ肯定できたこと
これらが、私にとってかけがえのない“リターン”になりました。
もしあのとき、「墓なんていらない」「ゼロ葬で十分」と割り切っていたら、私は何か大切なものを失っていた気がします。
墓を建てる or 墓じまい――どちらが正しい?
ここで誤解してほしくないのは、「墓じまい=悪」ではないということです。
むしろ今の時代、多くの人が合理的に判断して、墓を手放すのは当然だと思います。
- 子どもがいない
- 墓地が遠すぎる
- 管理費やお布施が高すぎる
こうした現実を前に、「持たない選択」をするのは正解です。
でも私にとっては、合理的ではなく感情論的に「建てる選択」が正解でした。
この選択が、読者の皆さんの何かのヒントになれば幸いです。
読者へのメッセージ:奨学金と供養の狭間で悩む人へ
最後に――。
もし、今あなたが
- 「奨学金で生活がカツカツ」
- 「親の供養にまでお金が回らない」
- 「親と疎遠だったから墓なんて…」
- 「自分も弱者男性で生きるのがしんどい」
と悩んでいるなら、伝えたいことがあります。
無理して墓を建てる必要はありません。
でも、「親への感謝」や「ルーツを大切にしたい」という思いがあるなら、それは立派な心の財産です。
そして、貧困でも、奨学金まみれでも、社会の片隅でも――。
あなたには“何かを返す力”があります。
それを形にするのは、墓でも、手紙でも、NISAでも、なんでもいい。
この記事が、あなた自身の「選択」を後押しできれば幸いです。
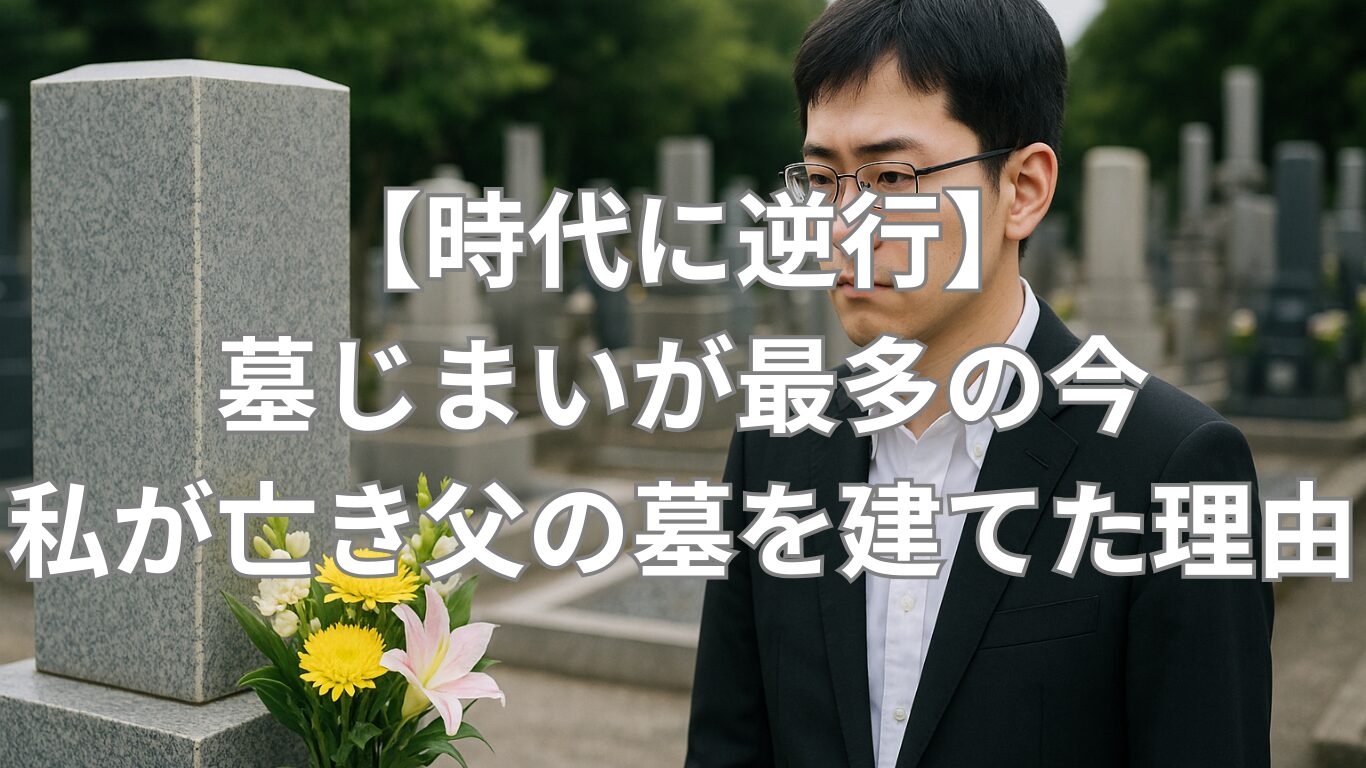
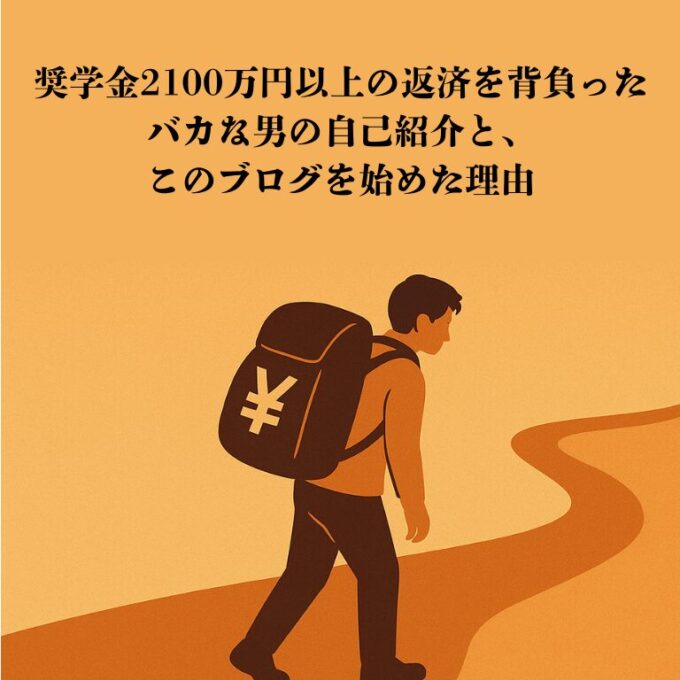


コメント