こんにちは、奨学金男です。
私は高校2年生の時に父を亡くし、母子家庭で育ちました。3浪して6年制の私立大学に進学し、国家資格を取得。返済総額2100万円以上の奨学金を抱えて社会人になりました。身長168cm、独身。体育会系の部活に所属していましたが、選手としては目立った活躍はなく、先輩や監督からの暴力こそなかったものの、厳しい上下関係や体罰を受け、萎縮しながら過ごしてきました。
私についてはこちらの記事を読んでください。
そんな私が、昨今報じられている高校野球界の不祥事を目にして強く感じたのは、「あの文化は弱者男性をさらに弱くする仕組みだ」ということです。
1. 体育会系文化と弱者男性の相性の悪さ
体育会系文化は、一見すると「礼儀正しい」「上下関係を学べる」といったポジティブな側面が語られます。しかし、その裏では序列を強制し、声の大きい者が支配する世界が広がっています。
弱者男性――ここでは経済的・身体的・性格的に“勝ち組”とされない男性――にとって、この文化は致命的に相性が悪い。
理由はシンプルです。体育会系では
- 身体能力や容姿が目立つ者が評価されやすい
- 声が大きく社交的な者が主導権を握る
- 「同調しない者=敵」という空気がある
実力さえあれば問題ないのかもしれませんが、目立たず、内向的で、経済的にも余裕がない私のようなタイプは、結果として居心地が悪く下層の立場に押し込まれます。
運良く運動は人並みにはできたため、体育の授業で笑われるようなことはありませんでした。逆を言うと運動が苦手な同級生は一軍ともいえるカースト上位の連中にバカにされていました。
そして、運動が苦手な生徒が運動を好きになれるように指導できず、バカにする空気を止められない体育教師を軽蔑していました。
2. 「いじめ」が弱者男性に与えるダメージ
いじめの構造は、体育会系文化の上下関係と非常に親和性が高いです。暴力や言葉の暴力だけでなく、
- 無視や排除
- 無理な金銭負担(飲み会や合宿)
- 精神的マウンティング
こうした行為は、経済的・精神的余裕のない弱者男性にとって逃げ場がありません。
しかも、社会は「男なら耐えろ」「若いときの苦労は買ってでもしろ」という根拠のない精神論で片付けがちです。
3. 経済的制約が「選択肢のなさ」を生む
経済的に恵まれない貧困家庭の子どもは、
- バイトをしても合宿や用具代で消える
- 家庭内の精神的ストレスで学業や就活に悪影響
こうして負のスパイラルが回り始めます。
特に私はバイト禁止の高校+貧困家庭だったので、部活の道具は大切に長く使っており、周りが新調するのをうらやましく見ながら肩身の狭い思いをしていました。
4. 家庭環境と孤立感
父を亡くし、母子家庭で育った私は、相談できる大人はいませんでした。
いや、父が生きているときも相談はできませんでした。
体育会系の圧力に対して「逃げてもいい」と言ってくれる人はおらず、
「耐えることが美徳」という価値観を周りから押し付けられて育ちました。
私は親に感謝していますが、今考えると貧乏でいろいろなことを我慢せざるを得なかった背景が「耐えることが美徳」という価値観を私に自然と受け入れさせていたのかもしれません。
家庭環境が複雑な弱者男性は、こうして孤立を深めます。
孤立すればするほど、自分の立場を正当化する声も、助けてくれる人もいなくなります。
私自身、運良くいじめられたことはありません。しかし、もしいじめられていたとしても親を心配させまいとして誰にも相談することはできなかったと思います。
また、第三者から見ればそんなに過酷な部活動ならば辞めればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、気の弱い私は「辞める」という一言を言う勇気がありませんでした。そして、仮に言えたとしても、その後の学校生活は肩身の狭いものになることは目に見えていました。
私には家庭と学校(部活動)以外の居場所がなかったのです。
5. 社会的偏見という二重苦
弱者男性は、「弱い」のが悪いことだとされがちです。
- 経済的に苦しい → 「努力不足」
- 身長や容姿に恵まれない → 「自己管理不足」
- 社交的でない → 「性格の問題」
こうした偏見は、いじめの被害者であっても「お前にも原因がある」という形で返ってきます。
これこそが、弱者男性が教育機会や職場で生き延びにくい最大の理由です。
6. 私が体育会系を「クソ」と思う理由
体育会系文化は、弱者男性にとっては教育でも訓練でもなく、ただの支配構造です。
厳しい上下関係は人格を鍛えるどころか、委縮させ、可能性を奪います。
特に「声の大きい者が正しい」という価値観は、社会に出ても再生産されます。
7. 弱者男性が体育会系に対してできる対策
体育会系文化に巻き込まれたとき、弱者男性が自分を守るためにできるのは「環境を変える」「距離を取る」「戦わずにやり過ごす」などの現実的な戦術です。以下は、私自身の経験から有効だと感じた方法です。
- 早めに逃げ道を確保する
部活・サークル・職場など、体育会系の圧力が強い場所では、早期に別の選択肢を作っておく。外部のコミュニティやオンライン活動を並行して始め、別の場所に居場所を作ると「いつでも抜けられる」という安心感が生まれます。 - 金銭的な負担は徹底的に削る
中高生では難しいかもしれませんが、飲み会や合宿、不要な用具購入などは「経済的に無理です」とはっきり断る。経済的制約は正当な理由になりますし、背伸びをして支払っても評価はほぼ上がりません。逆にそういうキャラだと思われて必要以上に誘われなくなります。 - 対立よりも“無害ポジション”を目指す
権力を持つ人に直接反抗するより、空気を乱さず淡々とこなす方が生き残れます。体育会系は「敵か味方か」で人を分類する傾向があるため、敵認定されない程度の距離感が重要です。 - 声の大きい味方を一人でも作る
同じ組織内に、こちらを守ってくれる立場の人がいるだけで圧力は激減します。先輩、顧問、あるいは職場の上司など、話を聞いてくれる人を探すのが第一歩です。 - 記録を取る習慣を持つ
理不尽な発言や行為は日付・場所・発言内容をメモしておく。証拠があれば、いざというとき外部機関や上層部に相談できます。 - 外部リソースを活用する
学校なら教育委員会、職場なら労基署、匿名相談窓口など、内部で解決できない場合は外に頼る。弱者男性ほど「内部解決」にこだわらず、外圧を利用した方が安全です。
体育会系文化に潰されそうになった過去の私に言いたいのは、
「逃げてもいい。でも、逃げた先で自分の居場所を作れ」ということ。
8. 弱者男性が生き延びるためのマインドセット
7. 弱者男性が体育会系に対してできる対策にも通ずるものですが、弱者男性として社会の中で生き延びるには以下のマインドセットが必要だと思っています。
- 比較をやめる
体育会系や“勝ち組”男性と比べない。 - お金を味方につける
奨学金返済中でも投資や副業で将来への布石を打つ。最悪お金があれば何とか生きていけます。 - 声を上げる準備をしておく
匿名でもいい、経験を共有することが力になる。 - 人間関係の外注化
家庭や学校で得られないサポートは、外部コミュニティやSNSで補う。
まとめ
広陵高校や高野連のいじめ・暴力問題は、単なる学校内の問題ではなく、
社会全体に根を張る体育会系的支配構造の縮図です。
弱者男性にとって、それは機会を奪い、精神を蝕み、将来を狭める大きな壁となります。
私自身も、その壁にぶつかりながら、借金を抱えたまま社会に出ました。
しかし、今はお金や時間の使い方を工夫しながら、生き延びる戦略を持っています。
同じように悩んでいるあなたへ――
逃げてもいい、耐えてもいい、でも自分の武器や居場所を作ることを忘れないでください。
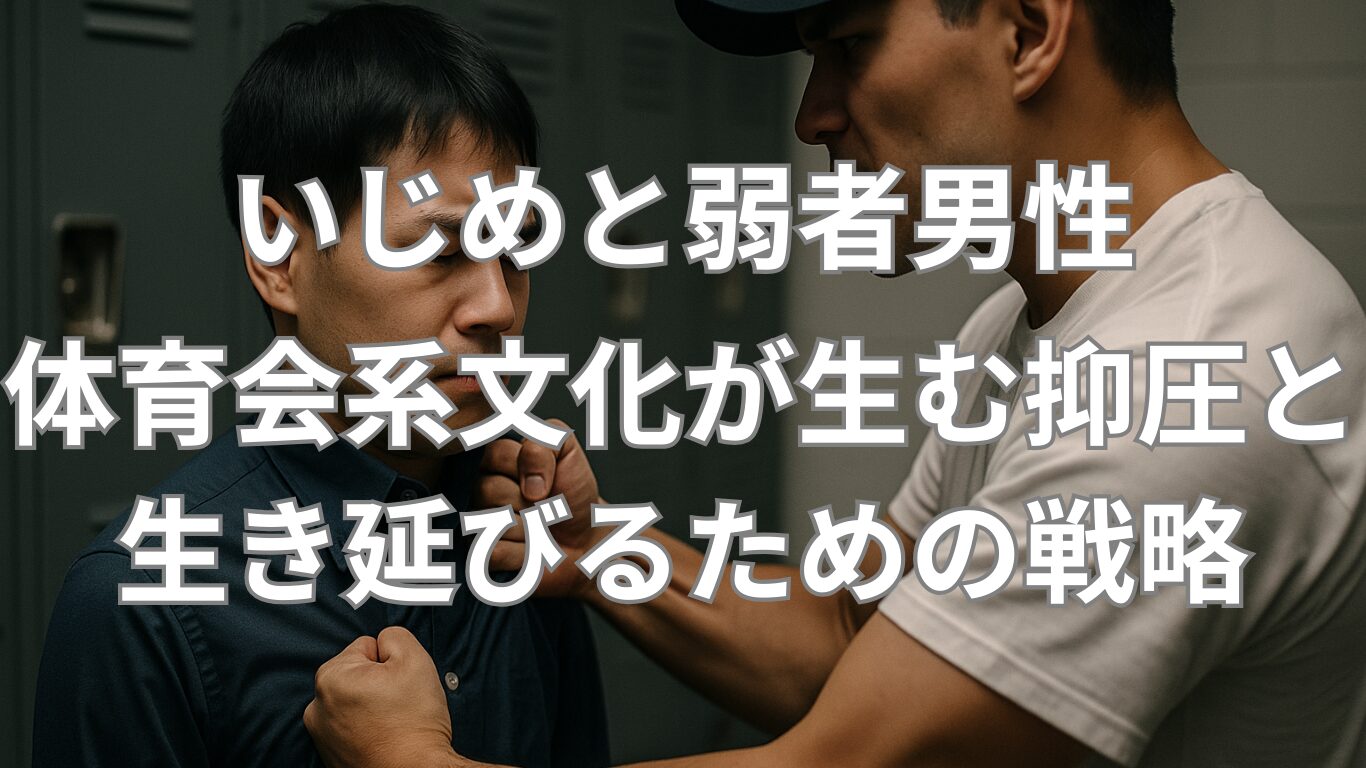
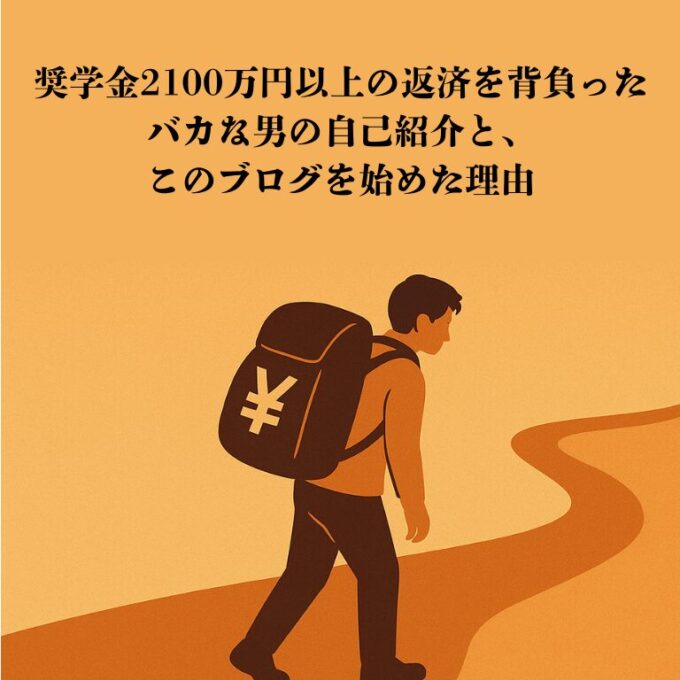
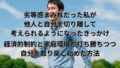

コメント